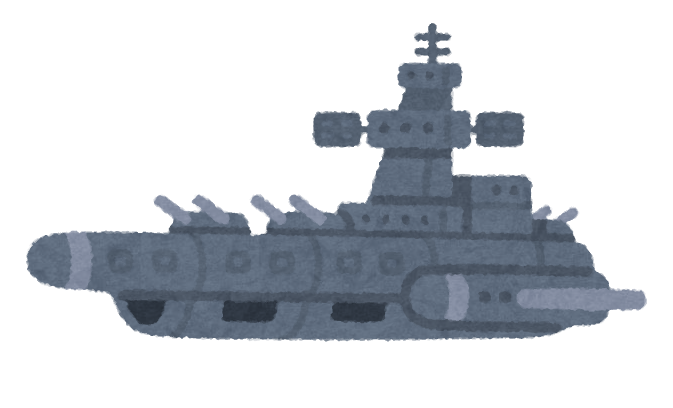Overview
征服モード攻略に使える知識や情報のまとめ。敵対組織や生物について。設計の注意点や武装の利点・欠点等。戦闘における注意点について。前提としてバニラ環境におけるプレイをまとめている。初心者向きかは不明。
初めに
2020年9月のバージョンについての記述。アップデートは気まぐれで対応する。
環境はバニラ(何のMODも導入せず)を前提にしている。
撮影のために配置制限をなくすNo Building RestrictionsというワークショップにあるMODを利用している。更新の都合、全モジュールには適応されないが、快適でバニラといいつつ使ってしまう。[link]
(2021 0209 追記 いつの間にかこのMODは消えていた。お世話になりました)
このゲームのメインはオンラインの対人戦かもしれないが、個人的にはCPUと戦う方が性に合い、楽しく遊べるこの征服モードについて記述する。
経験・記憶・目測によるものであり、解析ではない。正確性については察していただきたい。
スポイラー要素がある。ネタバレしたくない方は避けてほしい。
用字用語が統一されていない部分がある。
例えば、このゲームのメイン兵器は本編中、飛行艇と表記されている。
しかしガイド本文には、飛行船と書いた部分がいくつかある。
本音を申せば、間違いを訂正するより、新しいセクションを作るか、ゲームをプレイしたい。
よって誤字脱字と誤認誤解について、直す気持ちはあるものの、残るかもしれません。
ガイド公開後のアップデート 2021年
征服モードに関連する修正のみ、またはそれを中心に記載する。
2021 0721
2つの新しい国家ボーナス追加
近接攻撃(電鋸および火炎放射)強化 と 小型機(空母艦載機等)の発射速度強化 国が新規。
海兵の火器発射レートが低下
事実上阻止困難な拿捕攻撃が下方される。
公式チートコード解禁
開発者泣かせの非公式チート利用に伴うバグ報告への対策として解禁された模様。実績は解除されず、マルチプレイ時の使用は禁忌。本作はお一人で制作したゲームだった記憶がある。すごいね。
2021 0331
バランス調整とバグ修正のみ。
サスペンディウム光線がますます重装甲に弱くなる。すぐ潰されるデッキガンの耐久力が増す。
など細かな修正で大きな変化はないはずだ。詳しくはお知らせを。
2021 0209
細かくは追えないため、わかる範囲で記載する。数値の変化等もある。詳細はお知らせから。
1 帆類・マスト類の変化
推進力をもたらし、速度に関わるモジュールのうち、石炭を消費しない、帆類・マスト類に新規追加がなされ、既存のいくつかが削除された。同時にAI国家に新しい設計タイプが加わる。
スクリーンショットは後述するMODの利用停止により同一撮影が不可能になったため断念する。
2 船舶速度の変化
これまでの船の速度は、重量とエンジン等の推進力だけが関わっていた。
今後は船体の形がもたらす空気抵抗の要素も加わる。設計のオーバーレイで確認可能。
カタログスペックほどの速度が出ないときは抵抗が関わっているかもしれない。
3 火災の仕様変更
ダメージ減・拡大速度増・延焼時間増となる。
1か所でかつ水があれば以前と同じく大した被害はない。
複数個所で火の手が上がると、手の付けられない全体火災へ一気に進む傾向を感じた。
これまで以上に水の配置と予備人員が重要になったのかもしれない。
ロケット・爆弾・火炎放射など、可燃性の高い武器が相対的に強化されたと考えられる。
今回のアップデート外の件
アップデートの度に増え続けるアルファベット、つまり翻訳されないことは問題として把握されている。そこに日本語が含まれているかは不明。
予定されている征服モードの外交システムのアップデート等は時間がかかる模様。(コメ欄より)
アップデートには関係ないが、ガイドの内容に関わる変化
No Building Restrictionsの使用不可
これまで大変お世話になっていたMOD No Building Restrictions が削除されたようだ。
このMODは、大砲の真横や艦載機の真上など、本来置けない場所にモジュールを置けるようにできるものだった。無茶な戦艦づくりやモジュールの撮影を簡単にしてくれていた。
今まで、ありがとうございました。
ガイド公開後のアップデート 2020年
2020 12
艦名作成に変更が加わった。敵国の新しい設計傾向が追加された。
詳しくは各自でご確認を。
攻略上の一番大きな変更は、地上戦艦及び建造物の命中率が向上したことだ。
飛行船一強の現状に一石を投じた修正であり、地上砲台と浮遊砲台が同じ命中率という不思議な物理の現実への接近でもある。
試してみたが、砲艦のみで同じような装備の地上兵器と死角を狙わずに正面で撃ち合うとかなり厳しくなった。
少し過剰な気がするため、変更は早いかもしれない。
2020 10
1 勝利・敗北時にグラフとリプレイが見れるようになった。
詳しくは更新の報告を見る方がわかりやすい。ストラテジーゲームらしさが増して好印象。
2 歴と時刻と季節の追加
移動・建造・研究に必要な時間がわかるようになった。
(正直フレーバーだ。月単位で飛び続けられる飛行船とはいったい?深く考えても仕方がない)
また半月が収入のタイミングである。
このゲームは太陽の位置で兵装の命中率が変わる。夜明けは左から右への命中率が下がり、夕暮れは右から左への命中率が下がる。攻める側は常に左から始まるため、夜明けを避け、夕暮れを狙う価値が生じる。艦隊が鹵獲中心なら命中率の下がる夜間に攻めることもできる。
戦略マップ上で待機することはできず、調整が面倒ではある。
季節の追加によって、雨や霧や雪といった天候の起きやすさが変化するらしい。どう変化するのか書いてほしいところだ。
3 戦闘中の待機の仕様変更
戦闘中に飛行艇や地上戦艦を開始時の端に寄せると、待機命令を下せ安全圏に置くことが可能であったが、その回数が1戦闘で1度きりとなった。これは何度も出入りできた以前がおかしかった。
4 ステータスの変更(気になったもの)
建造物に使われる装甲、石の爆発ダメージに対する防御力が少しだけ上がった。
強力な兵装ミサイルの爆発ダメージが半減した。
雷撃機を除いた、艦載機の建造費が下がった。技術によっては全艦載機の維持費も軽減される。
攻略目標
ゲームクリア条件
すべての造船所のある都市を自国の所有にすること。
全都市の制圧ではない。最後の該当都市が陥落したときゲームは勝利で終了する。
この地図上で大きな盾が描かれている地点が、造船所のある兵器製造が可能な都市である。収入面でも大きな位置を占めている。マップは一番小さいサイズ・スモールの大陸である。
.
中間サイズのミディアムでこれ。
.
最大サイズのラージはこうなる。(一番広い視点。下にもう数都市ある)
初期設定
ゲーム開始時に設定できるものは次の7つだ。
武器の編集
そう書かれているが、外見は国旗の紋章決めであり、実質的には国家ボーナスの設定である。
詳しくは実際にプレイして決めてもらいたいが、かなりの種類が存在している。
即時都市占領、都市収入増加、建造時間半減、大砲命中率倍化、などが強力だった。
敵もボーナスを受ける。諜報費用減と成功率増加や、戦闘能力強化の敵がいるとかなり面倒だ。
マップの広さ
実際のサイズは上にある攻略目標のセクションを見てほしい。
広いほど管理しなければならない都市が増える一方で、最終的な国庫は増大し、派手な艦隊が作れるようになる。
難易度
6段階。敵国の行動が難易度で変化するかは不明。明らかに差が表れる部分は、初期戦力や資金と都市収入である。難しいほど、残高や収入が低く、開幕の自戦力が安上がりに感じる。上級辺りからは敵に露骨な下駄を履かせている。初期の技術や都市防衛設備がおかしい。
上級(上から3番目)で始めたところ、開幕にガトリング(次の段階の技術)を装備した敵がやってきた。超上級で(上から2番目)開始直後にスパイを送ると都市にサスペンディウム砲(後半の技術)を備えた建造物があった。
陸の広さ
3種類。大陸は海がなくなる。群島は陸地が海で分断されるため、地上戦艦を防衛にしか使えなくなるだろう。どれにせよ基本的な戦力は飛行船であり、補給線の要素はなく、誰も渡海を躊躇しないことを忘れずに。
モンスターの出現頻度
征服モードでは全国家に敵対するモンスターが存在している。海賊や山賊、カルト宗教といった敵対者から、ドラゴンや巨大グモのようなファンタジー生物、ストーンガーディアン・シェルウォーカーといった超科学的メカが登場する。詳しくは後述。
出現頻度を上げれば、マップ上の都市ではない空の拠点に出現してくる頻度が増す。
研究速度
プレイヤーが定める戦略の中には技術開発の順番がある。新技術によって、モジュールが解禁され、既存の兵装が強化され、費用が削減されたりする。ここではその開発速度が調整できる。敵国も同じように技術レベルが上がっていくかもしれず。早くすれば単純に強くなるわけではないだろう。
初期研究段階
上記の技術が最初から発展した状態で開始できる。後半に解禁されるパーツは高価であり、運用できるかは別問題だ。敵も強くなるはず。
国庫
資金は現状、征服モードにおける唯一の資源である。戦力の増強や維持には欠かせない。
収入
自国の都市からの定期的な収入
各都市には収入が設定されている。敵国都市の収入はスパイを潜入させないと見えない。
金額は占領の結果やモンスターの襲撃によって一時的に減少することがある。
バニラに内政をして収入を増やす要素はない。
気になる方は、ワークショップにあるMODを導入しよう。今のところ日本語のものはない。
モンスター撃破時の報酬
敵の巣くう拠点に兵器を送り、戦闘に勝利すると国庫に編入できる財宝が見つかる。(基本的に)
最低でも千程度から中には万を超える収入がもたらされることもある。
都市の略奪
都市を即時平定できる国以外は、敵都市を陥落させたとき、3つの選択肢が用意されている。占領(建造・補給・補充が可能になる)に時間はかかるが都市の収入を損なわない平和的占領。早期占領の代価に収入が低下(2割程度)する暴力的占領。一時金(収入の2倍)と早期占領を得られるが、定収の大幅減少(4割程度)を被る略奪がある。収入は段階を踏んで回復する。状況に応じて選択しよう。
支出
一時的 兵器と建築物の建造費
スパイの潜入費と工作費
継続的
変動可能 計算の基礎となる値は、全都市からの収入に連動する。
秘密警察 4段階。高いほど敵国が自国に対して行う工作の阻止率が上がる。
研究開発 4段階。高いほど研究中の技術が手に入るまでの時間が短くなる。
変動不可 収入に関係なく決定され、段階を変えることもできない。
維持費 船舶や建築物ごとに計上される。
スパイの潜入費 潜入させている都市の数の比例する。
ちなみに国庫が空だと、兵器を移動させることができなくなる。
変動可能な4段階について。ある終盤の記録を再生するとこうなった。あくまでも一例であり、参考にならない可能性が高い。
秘密警察は 0 収入の8%程度 その3.5倍 さらに2倍
研究開発は 0 収入の4%程度 その3倍 さらに1.7倍
初期は別の計算式なのか 秘密警察の最低値は2%程度で研究開発は10・35・65である。
都市数や難易度など、計算に関わる数がいくつかあると考えられる。
秘密警察は最低限のレベルだと、敵の工作(焼討や生産妨害)が7割程度、成功されてしまう。
高額な第二段階に進めるかは悩みどころだ。最高値だと維持費の支払いで軍が成り立たない。
研究開発は、基本的に0か第一段階で十分である。急いでいるときだけ高額な選択を選ぶべき。
兵器や建造物の生産ルール
可能な場所
兵器の生産はマップ上の大きな盾が描かれた都市(造船所)でのみ可能。建造物はすべての都市で建造できる。造船所都市を失えば事実上脱落である。
場所による違い
製造可能な都市には、造船所の大きさというパラメータがある。
巨大、大規模、中規模、小規模、極小の5段階で、兵器の製造速度にかなりの差が生まれる。
成長させることはできない。大きな造船所を持つ都市は重要な攻略目標になるだろう。
必要な時間
製造にかかる時間は、製造費用に比例して長くなっていく。
極小の造船都市で予算数千の戦艦を建造することはおすすめできない。
建造物も同じルールのもとで建設される。造船所の大きさは建物にも影響する。
極小の造船都市は、普通の都市と同じ速度でしか物を建てられない。
修理や再装備について
戦闘の結果破壊された部分の修理や、既存の戦艦にモジュールを点けたり外したりする再装備も造船所のある都市でしか行えない。必要な時間も、新規製造と同じルールが適応されている。
設計について 概論その1 最低限必要な物 等
最低限必要な物
飛行艇・陸上戦艦・建造物の各種兵器設計を行う場合一定のルールにしたがった兵器を作らなければならない。
共通
兵装や各種部屋によって要求される必要最低限の兵員を満たせるだけの居住スペース。
同じく必要な補給量を満たせる搬入口。
船員が移動できるすべてのモジュールが1か所は他とつながっていること。(孤立させない)
飛行艇
浮遊力。脆いが無燃料のタンクと、装甲可能だが石炭を消費するサスペンディウム炉がある。
推進力。石炭が必要なプロペラ類と、燃料不要だが人手のいる帆類と大きく脆いマスト類が存在。
指令室。コックピットかブリッジかコマンドセンター。後ろほどコストが高く、早急な指示可能。
陸上戦艦
推進力。車輪と足がある。重量制限あり。どちらでも石炭貯蔵庫は必須。
指令室。飛行艇と同じ。必要乗員の増加で再指示時間が長くなり、複数置くと処理能力が増す。
指令室なしでも、設計完了はできる。動けない棺桶でいい場合は保存を押そう。
浮遊力・推進力・指令室のいずれかを完全に喪失することは、戦闘後の除外判定で不利に働く。
建造費5000超えの戦艦が、初戦で敵の墜落に巻き込まれ、大型プロペラ2台だけを破壊されたために、他は無傷でも除外されたことがある。
大型艦船をわずかな損害で失わない保険として、小さいタンク・小型のプロペラ・コックピット等を機能上は無意味でも、配置しておくことをおすすめする。
建造物
共通のルールさえ満たせば、指令室すら必要ではない。戦闘後の除外判定にも当たらない。
なければ戦闘の際に内部状況を確認できないが、攻撃は自動的に行う。
弾薬と石炭
弾薬が尽きると、攻撃できなくなるだけでなく、戦闘の勝敗判定では脱落とみなされる。すべてのユニットが撃てなくなれば無傷であっても敗北とされる場合もある。
石炭は戦闘時の浮遊時間の長さのみを左右する。石炭切れの着地は戦闘後のユニット除外判定で不利に働く。おかしなことだが、戦略マップ上ではいくらでも飛び続けられる。
各種機関のスクリーンショット
撮影の都合上、いくつかのモジュールはMODで本来置けない場所に配置している。
いくつかのモジュールは技術開発が必要だ。
飛行船の浮遊力

左は石炭と人手を要求するが、装甲が付けられる各種サスペンディウム炉である。
右は他に何も要らないが、装甲不能で脆く爆発する危険性のあるサスペンディウムタンクだ。
右下の圧縮サスペンディウムタンクは例外的に装甲を付けられる。
バニラの大型サスペンディウム炉は煙突の関係で真上に物を置けない。
飛行船の推進力(2021 02 大きなセイルとダブル・トリプルマスト削除 マストが数種類追加)

右は マスト・ダブルマスト・トリプルマスト
プロペラ類は、石炭が必要だが、装甲可能(ポッドを除く)で、人手の割に出力がある。
帆類は、燃料を必要とせず、装甲可能だが、人手の割に出力がない。
マスト類は、帆類より高出力であるものの、装甲不能で脆く、さらに多くの人員を要求する。
バニラの推進機関は配置位置の制限が多い。正直なところ面倒で、ついMODを使ってしまう。
地上戦艦の推進力

左下は スパイダーレッグ・トラック・ラージトラック
すべて石炭を要求し、装甲可能だ。
違いは費用やHP以外に、動かせる重量の制限と石炭の要求量および移動の適正などがある。
トラックは安いが、段差に弱い。スパイダーレッグはほとんどの土地を移動できる。
これらは真下に物が置けない。
指令室

指令部だが複数置ける。中型艦以降はブリッジを2個置かないと10秒以上再指示できなくなる。
コマンドセンターは12人の船員を要求するが、特殊効果で艦隊全船の指令能力が30%向上する。(再指示が可能になるまでの時間が短くなる)
コックピットとブリッジは制限なく設置できる。コマンドセンターは正面に物が置けない。
設計について 概論その2 共通のボーナスや維持費 等
共通のボーナスとオーナス
モジュール同士を隣接させるとHPが増大する。ただし炎上や爆発の影響を受けるため、痛しかゆしである。特に大砲や爆弾、弾薬庫と石炭貯蔵所、サスペンディウム関連設備は危険だ。隣接させるモジュールは意味のない通路でもいい。完全に囲む必要まではない。か細い部分を作らないようにしよう。
一定の規模を超す設計をすると、モジュールを追加するたびに全モジュールのHPがわずかに減っていく。その場合は設計画面の右上に警告が出る。敵との位置関係以外はどの場所も被弾する可能性がある仕様との兼ね合いだと推定される。(無意味な通路でバイタルパートの被弾率が下がる)
そこまで減るわけではないが注意したい。特にHPを増加させる船首やキールはもったいないことになるかもしれない。
オーバーレイ
設計場面の上にある「オーバーレイ」という項目を選べば、その時点のモジュールのHPだけでなく、水や弾薬の届く時間、爆発の影響などを知ることができる。
製造費と維持費について
各種兵器にはモジュールと装甲の合計による製造費の他、都市収入に合わせて消費される、維持費が存在する。主に乗員から発生し、艦載機以外の兵器から要求はでない。人を余らせるほど非効率なことになる。一方でかつかつにすると、装填や消火に時間がかかり、負傷の発生によってわずかな戦闘時間で対応力が低下する。建造物は浮遊や移動に人手を取られず、維持費の計算式が異なるためコストを抑えられる。
維持費の発生する各種パーツ。
左上に書かれているコストが製造費。
その下のメンテナンスが維持費である。
撮影の都合、MODを使って本来できない置き方を解禁している。
バニラでは艦載機の真上に物を置けない。
左上から
寝台室(乗員3人供給・維持費3)
居住区(乗員12人供給・維持費8)
カード兵舎(防衛用ガード4人配備・維持費1)
マリーン兵舎(敵兵器の鹵獲にも使える海兵8人配備・維持費4)
エア・ドラグーン兵舎(空飛ぶ兵士3人配備・維持費4)
グレナディーア兵舎(グラップルフックを使う精鋭兵士4人・維持費4)
スパイダーベイ(クモ型ロボットを4機収容・維持費2)
マリーン以下の部屋については後述。
右は
ハッサー・ベイ 三葉機 爆撃機 複葉機 吊るし型複葉機 雷撃爆撃機(艦載機・維持費2)
詳しくは後述の武装について。
再装備との兼ね合い
このゲームには技術開発の要素があり、新モジュールが次々に解禁されていく。保存する設計を毎回それに沿わせていくのは手間だ。予算の都合もあり、手に届く範囲の設計または製造してから、再装備という方法をとる方が合理的である。
各種武装の特徴 大砲・銃座・ロケットとミサイル
設計の中心である各種武装について、利点と欠点、向いている相手と苦手な相手を記述する。
大砲
基本的な兵装。最初から最後まで使えるが、圧倒的な砲火能力が揃うまでは特化型の敵に弱い。耐久力の関係上、建造物と同等の砲撃能力で撃ち合うと勝てない。軽視すると負け、重視すると穴に落としてくる、ひねくれ者。それでも砲撃はこのゲームの華である。音がいい。
利点
長い射程。高い貫通力。そこそこの命中率。方向さえ合えば墜落しても戦力にカウントできる。
短時間で簡易修理できないダメージ(造船所以外では回復不能)を与えられる。
欠点
射角が狭い。1射1補給で弾薬消費が多い。装填時間が長め。重い。高価。
被弾時に爆発する可能性が高い。
向いている相手
中盤以降出現する装甲の硬い兵器。自分よりも正面砲数の少ない建造物。的になるなら何でも。
苦手な相手
航空母艦。鹵獲を狙う高速艇。移動能力、特に上昇可能域が自分よりも高い敵艦。
同等の砲性能を持つ建造物。

上からキャノン砲・ブドウ弾キャノン・インペリアルキャノン砲・軽量スポンソン・ヘヴィーキャノン・ドーサルタレット・正面砲塔・重旋回砲塔である。白い線が射角。
インペリアル以降は技術開発が必要だ。下の3つは特に後半の技術で解禁される。
基本的に大きければ大きいほど、威力と射程そして装填時間が増えていく。
撮影の都合、MODで正面に物を置けない制限を取り払っている。
銃座
これまた基本的な兵装。中盤の兵器相手では力不足だが、射程内の敵を確実に削れることが強み。自分より強い敵には弱くなり、弱い敵には強くなれる、卑屈な性質の持ち主。しかしその生の後半には、自軍の大型艦を敵小型機から守るという重要な任務が待っている。
利点
弾薬消費量が少ない。早い装填。射角が広い。被弾時に爆発しない。
攻撃力-防御力≦0でも1ダメージ保証はあるため、確実に敵のHPを削れる。
欠点
ライフルを除くと短い射程。ガトリングを除くと根本的なダメージ量が少ない。他の武装と比べて鋼鉄や石壁以上の装甲を持つ敵を無力化するまでに必要な時間が長くなり、その分攻撃される。
相手にリペアベイがある場合、被弾箇所を修理される可能性が高い。
向いている相手
航空母艦や飛行場から飛び立つ小型航空機。軽装甲の高速船。敵兵士。瀕死の兵器。
苦手な相手
重装甲。死角がなく、ある程度の火力を持った建造物。アウトレンジ攻撃。

上からマスケット・ライフル・バリスタ・ガトリングガン・Walled Deck Gatling Gun(未翻訳) 。技術開発の必要なガトリングガンは射程の短い連射武器で破壊力がある。ライフルの射程は大砲並みにある。バリスタの性能は大砲よりだ。
銃座の単発威力は大砲の10%から20%だが、10倍以上の弾倉数と、半分から3分の1のリロード時間であり、射角の上下差がはっきりわかる。
ロケットとミサイル
上記したふたつとの差として、これらは爆発ダメージという属性である。(銃砲は貫通ダメージ)
このダメージは鋼鉄に弱いが、木材と建造物の主要装甲である石に強い。また爆発である以上、1発で複数個所に損害を与えられる。爆装艦は動けない相手を得意とする卑劣艦だが、勝つことが本にて候というものだ。
利点
爆発で複数モジュールにダメージを与えられる。炎上させやすい。
結果として敵船員の対応力を効果的に落とせる。建物に強い。そこそこの射程。
武装と弾薬さえ無事なら船が地面に落ちても戦力として成立する。見た目が派手。
欠点
被弾時の極めて高い爆発性。リロード時間が長い。鋼鉄以降の装甲は貫通より爆発ダメージを大きく軽減する。砲や銃より弾が遅く、離れていると上昇下降で回避できる。
ロケットは命中率に難があり、撃った瞬間に外れることがわかるレベルの弾が頻発する。
向いている相手
建造物。木材装甲の船舶と陸上戦艦。
苦手な相手
鋼鉄以降の重装甲。巨石を使う建造物。火炎放射。高速移動。艦載機には手も足も出ない。

上からGuided Missile・ロケット・巨大ロケット・Rocket(External)・Massive Rocket(External)である。最近のアップデートで追加されたものが多く翻訳が終わっていない。後ろ2つは戦闘中に一度だけしか使えない(コンパネに撃つボタンが追加される)代わりに人員を必要としない。ミサイルは長射程・高威力・誘導の性質を持つが、リロードが全武器中最長の25秒かかり、200メートル以内に接近されると撃てなくなる。
各種武装の特徴 衝角・拿捕・航空攻撃
ここでは各種武装の、弾を撃たない武器を中心に紹介する。
衝角
本作には船同士の接触ダメージがある。その打撃を積極的に与えることを目的にした武装がこの種類である。ひとつ丸鋸があるのはご愛嬌。メインソースとしてはいささか扱いの難しい武器だが、刺ったときの威力は絶大。敵も味方も無傷では済まない。おそらく敵にする方が厄介な兵装。
利点
弾薬がいらない。敵に撃たれても爆発炎上の危険がない。丸鋸以外は非常に頑丈。命中即破壊になる大きなダメージ。勢いをつけてうまく当てられると一撃で建物を貫通する。
欠点
動く相手に当てづらい。角が持っても艦橋・機関部等のバイタルパートは持たない。
最低でも時速90キロ程度は欲しい所だが重い。地形や壊れた残骸で動けなくなる可能性。
接近=高命中状態。必要性から常に前に立つため消耗が激しい。
向いている相手
鈍足な敵。片方に火点が集中している兵器。建造物。
苦手な相手
高速。広い範囲に兵装を持つ。残骸が残る大きな建造物。圧倒的な火力投射。(近づけない)
(地上運用の場合)背が合わない。複雑な地形。

上から、ラム・スパイク衝角艦・排障器衝角艦・グランドラム・ソウブレイドである。
ソウブレイド以外は、HPが4桁後半からグランドラムに至っては45000ある極めて頑丈な武装だ。その代わりソウブレイドのダメージは非常に高い。爆発する上、石炭もいるけれど。
弱点の重さは、500・900・250・3000・150である。(キャノン1個は70)地上戦艦の建物破壊用武器と考えた方が使いやすい。敵国には丸鋸だけ艦の突貫を好む国もある。
拿捕
まるで中近世の海賊だが、直接兵員を船に乗り込ませる拿捕戦術は強力だ。特殊な兵を投入するため、空中で乗り移らせることも可能。地上の建物にも使える。成功すれば無傷の敵兵器が手に入る。ハイリスク・ハイリターン戦術である。万一に備えて、複数の特化艦を運用したいが、維持費が見た目以上にかかる。貧乏国向きの貧乏神的存在感がある。これも敵に回した方が怖い。
利点
勝つか勝てないかのどちらかであり、事前に阻止する方法が事実上ない。勝てば敵兵器や建造物を丸々手に入れられる。兵員に維持コストはかかっても、雇用コストは存在しない。敵地だろうが部屋さえ維持できれば兵は湧いてくる。ことはなくなった。自国都市での補充(敵地は占領が完了するまで不可能)が必要。失敗に終わっても、船員を負傷させ、兵装の無力化という結果を生み出せる。特化艦の建造だけは相対的に低コスト。
欠点
大量に兵員を積まなければ、基本的に1回の戦闘でターゲットにできる存在は1つだけ。
(捕獲後、当該船舶等から再移動を指示できるが、消耗によって同じ戦果は期待できない)
多数の乗員がいる相手には白兵戦で負けることもある。戦闘能力はガードの方が高いはず。
メンテナンスコストが兵員設備にも必要なため、相対的に維持費が高い。
2020/09のバージョンアップの結果、占領進行中ではない自国都市に入らないと補充補給ができなくなった。(戦闘終了後に即補充だった以前の仕様は、不自然かつ強すぎ、修正は妥当だろう)
2021/07のバージョンアップによって基礎的な部隊マリーンの戦闘能力が下方された。
向いている相手
兵員がそこまで多くない鈍重な兵器。同じような建造物。少数の防御施設しかない都市。
苦手な相手
大規模兵器。接近前に兵を撃ち落とせる多数の銃座持ち。
自分より高く飛べる相手。(上に飛べないマリーンとスパイダーの運用時は特に)

上から、ハープーン・ガン、マリーン兵舎、エア・ドラグーン兵舎、グレナディーア兵舎、スパイダーベイである。
右は天敵のガードポストとガード兵舎だ。
ハープーンは敵艦にフックロープを撃ちこみ、距離を詰める兵器。エア・ドラグーンは空を飛べ、グレナディーアはグラップリング・フックを装備しているため、ある程度の距離を無視できる。
航空攻撃
飛行船のゲームで航空攻撃とは?と思われるかもしれない。このゲームでは小さな航空機を利用した攻撃、つまり空母的運用ができる船も作れる。兵器にも建造物にも強いが、飽和攻撃の必要性から複数隻または大型空母の運用が前提で、桁違いの建造費と維持費が要求される。また脆いため護衛は必須。まさに金のハンマーを持った卵のような存在である。敵としては空母より飛行場か航空戦艦に出会うことが多い。単独運用は推奨されないご身分だ。お付きを用意しよう。
以前にとりあえずハッサー・ベイ艦が猛威を振るったため、下方を受けた歴史をもつらしい。
利点
敵の対小型機能力を突破できると、相対的超高速機体がまとわり続け、甚大な被害を与えられる。
高速艦、重装甲の地上戦艦、大規模な建造物、敵の陣容は関係ない。
着艦の手間を考えなければ、空母は離れて様子見できる。現状の仕様では弾薬庫がいらない。
欠点
銃座(特にガトリングガン)や対空砲を持つ、対小型機能力が高い相手には戦果が期待できない。
補給目的の着艦時間をリロードと考えると、全兵装中の最長といえる。
上にものを置けず、装甲を装着できないため、構造がペラペラになりがち。喪失可能性が高い。
キールや船首でしか補強できず、脆さは要修理を誘発し、安くない維持費以上に金をもっていく。
発進中に距離を詰めてくる、高速の鹵獲や衝角と火炎放射は単体で阻止できない。
艦載機以外の武装は控えめになりがちで護衛艦が必要。
向いている相手
銃座や対空砲の少ない敵。砲台しか持たない建造物。基本的に苦手でなければ相手を選ばない。
苦手な相手
銃座や対空機銃の多い敵。こちらの拘束・抑止を突破してやりたいことをやってくるやつら。ドラゴンやマッドサイエンティストの拠点以上に強いモンスター。(攻撃を護衛で阻止できない)

各種武装の特徴 爆弾・火炎放射・その他の武器
最後は色物も多いが、強力なもの少なくない種類の武装をまとめておく。
爆弾
砲弾・銃弾とくれば当然爆弾も存在する。この武器の強みは一方的に攻撃できる点だ。そのために他の武器と比べて位置取りを強く意識しないといけない。鹵獲とならんで上昇限度の重要性だけでなく、頻繁に動けるように指令速度も考慮に入れよう。攻撃属性は爆発ダメージであり、複数モジュールにダメージを与え、建造物や軽装甲の敵に強い。
利点
ほとんどの砲は真上に攻撃できない。上空から一方的に攻撃できる。
欠点
命中精度が低い。爆発しやすい。各種機関の破壊に伴う着地や移動不能が致命的。
相手が真上に対する攻撃手段を持ち、殴り合いになると辛い。
向いている相手
建造物。自分よりも高いところに飛べない敵。
苦手な相手
高速移動。上空攻撃可能。重装甲。

左からグレネード、Kinetic Bomb、ボンバーベイ、上空攻撃。
主には攻撃範囲の違いがある。グレネードは少し離れた下まで、Bombとボンバーは真下。上空攻撃は文字通りだ。Kineticはバージョンアップで追加された武装で、一度だけ使える強力な貫通ダメージの爆弾である。それ以外は爆発ダメージだ。
火炎放射
唐突な色物臭のする武器だが、接近戦を強いられる以外は高水準の武装である。撃てば確実に相手を焼け、火に強い兵器など存在しない。距離をつめて炙ってやれば敵は爆発していく。こちらも撃たれれば吹っ飛ぶことは忘れよう。モンスター撃破時の報酬で得られる酸攻撃武器もここに含む。
利点
確実な命中。銃座に似た性質で銃座より大きな攻撃力。火炎放射は小型機や突入部隊を迎撃可能。
欠点
射程が短い。可燃性。一定時間、敵前に留まる必要性がある。属性は爆発ダメージで鋼鉄は辛い。
向いている相手
木製や軽装甲の敵。死角を狙える建造物。空母や飛行場。
苦手な相手
強力な砲艦。自分よりも高速な相手。重装甲。

上から、火炎放射砲、巨大火炎放射器、アシッドスピッターである。
火炎放射機は技術で解禁され、強化する技術も存在している。
アシッドスピッターは技術ではなく、モンスター撃破の報酬、酸醸造というボーナスが必要。
可燃性が落ち、威力が強化された火炎放射器的存在である。
その他の武器
技術の最終段階や、今までに含められなかった武器をここでまとめる。

上と一番下はエアリアル・トルペード、エアリアル・トーピード(エクスターナル)。
真ん中がサスペンディウム光線とサスペンディウム砲。
下のふたつがフラックキャノン、デッキガンである。
エアリアル・トルペードは強力な爆発属性(鋼鉄でもカバーしきれない)の魚雷だ。エクスターナルは他のものと同じで一戦で一回限りの武器だ。特徴としては長射程・高威力・高精度の強力な武装であり、長いリロード時間と遅めの弾速、第四層の技術という重い解禁以外に弱点はない。
サスペンディウムシリーズは、同じく第四層の技術であり、光線は石炭、砲は石炭と弾薬も使う兵装で強力な貫通ダメージを敵に与える。当然、長射程・高威力・高精度の三本柱はそろっている。高価でかなり重く、砲は狭い射角、光線は最上級の鉄鋼装甲には不利なこと、両者に必要な石炭貯蔵庫は技術で強化できないことが弱点だろう。
フラックキャノンとデッキガンは、迎撃機能という特殊な能力を持っている。威力は同時期の大砲に比べて低いが、通常の戦闘だけでなく、近くにいる小型機への攻撃を自動的に行える。装備すれば、どうしても上昇範囲や機動力に劣る、大型艦の自衛能力が増す。
設計と運用について 地上戦艦編
このゲームのメインは飛行艇だが、地上戦艦もその独自の強みを生かせば、征服の助けになる。
ここではその地上部隊について簡単にまとめる。
飛行艇との比較
移動能力 飛行艇 > 地上戦艦
経済性 飛行艇 = 地上戦艦
耐久 飛行艇 < 地上戦艦
速度と高度は飛行艇には勝てないが、経済性はほぼ同等であり、耐久面では上回っている。
飛行艇は、推進力か浮遊力を失うと移動できなくなる。地上戦艦の足であるトラックやレッグを失うと同じ事になる。この部分に耐久力の差がある。
一番ランクの低いトラックで、HPは330まで上がるが、サスペンディウム炉は220、プロペラと大きな帆は180程度しかない。その上、飛行艇には落下ダメージがあり、サスペンディウムとプロペラは爆発もする。
移動速度を諦めて装甲に力を入れれば、その差はもっと大きくなる。
つまり地上戦艦は、文字通りタンク役として強化する方向が望ましい。
飛行艇と歩調を合わせて、じわじわと領土を拡張するか、重要な拠点付近の守りを固める運用をこころがけると力強い。
逆に言えば機動的な行動は望めず、海を渡る方法がない。活躍する場所を選ぶだろう。
設計と運用について 建造物編
防衛の主力、建造物の設計と運用について簡単にまとめる。
飛行艇との比較
移動能力 飛行艇 >>> 建造物
耐久力 飛行艇 < 建造物
経済性 飛行艇 << 建造物
移動力はいうまでもない。攻撃に死角があったとしても移動できる飛行艇に対して、建造物はそれを補う能力を持たない。CPUは容赦なく死角から攻撃してくる。
耐久力はコストをかけなければ終盤まで建造物が上回っている。基本の装甲である石壁はHPが高い。飛行艇の中盤までの技術装甲の倍近くある。(第二段階の強化木製装甲でようやく並ぶ)
経済性は建造物が優位にある。維持費の計上が、小数点切り上げ?の半分になっている。移動機関の不在と相まって、同等の兵装を構えても、維持費は各種兵器の半額以下に収まるだろう。
結果として、建造物は死角を作らないように、あるいは死角を補えるような配置で運用されなければならない。大砲なら両面に置き、置けない場合は別の建造物を設置する。真上は隣か、対空砲の開発までは上空攻撃(爆弾)かライフルで補うしかない。
耐久力が高いため、多少砲門数が足りなくとも、敵の飛行艇に打ち勝つことができる。
また建造物の存在そのものが、敵CPUによる侵攻先選定への抑止効果を生んでいる。
運用はそれを踏まえたものにしよう。
空き地を作ることは望ましくない。
多少拡張は遅くなっても、建造物が完成するまで、新領土に留まるべきだ。
戦闘について 概論
最終的な帰結である戦闘についてまとめる。
勝敗
基本的な勝利条件は、相手がいっさい攻撃できなくなることだ。
つまり、すべての兵装の破壊か、兵装内も含めた弾薬の欠如が必要である。
敵の全戦力がバラバラになって、地上に落ちても、それだけでは勝ちにならない。
逆に、大砲をあさっての方向に向けたまま動けない相手に、砲弾を浴びせ続けられる優位に立っていても、破壊しそびれ弾薬が先に尽きると、こちらの負けになる。
特に建造物の弾薬は、多少無駄でも多めにしておいた方がいい。
この奇妙な勝利条件の為、味方CPUの攻撃が、脅威度の低い敵に集中しやすい。無視されがちだが、積極的に攻撃相手の指示を出そう。
炎上と修理と治療
戦闘中は、砲爆撃銃撃の影響で様々なアクシデントが発生する。
火災は日常茶飯事で、きちんと水を用意しないと連鎖して、あっという間に船が落ちる。水の位置も重要であり、設計ではオーバレイを使って水の届く時間の確認をおすすめする。
各種モジュールは、HPが0にならない限りは修理可能だ。中規模以上の船にはリペアパーツを積んだ方がいい。
攻撃を受けた際にそのモジュールにいる船員はまず負傷する。医務室があれば復帰できる。負傷するよりモジュールと運命を共にする可能性の方が高いことは忘れよう。
艦の喪失
戦闘による艦の喪失のルールはなんとなくでしか把握できていない。
負けたときは自然に感じるのだが、勝った時の喪失は、敵味方を問わず時々おかしいことがある。
バージョンアップによる変化もあった気がするので、正確なことは各自で判断してもらいたい。
敗退(撤退)した場合、浮遊力か推進力か指令能力を失った艦(バツが付く)はまず喪失する。
勝利したときでは、確率による判定を行っているのかもしれない。
粉微塵になったときは、どちらのケースでも喪失する。
遭遇戦(都市や拠点以外の迎撃行為)では、勝っても負けても動けない艦は喪失していたと思う。
どちらにせよ、重装甲で高額な船を前面に立たせて修理や喪失のリスクを負う代わりに新造コストを回避するか、安い船の使い捨て覚悟でおとり戦法を実施するかはプレイヤーに与えられた選択のひとつだろう。
その選択を許さない敵(強モンスターや大艦隊)が一番怖い。
戦闘について 距離の影響
戦闘では敵との距離が離れるほど射撃の命中率が下がる傾向にある。一例を挙げるとこうなる。
試行回数は少なく、参考程度にとらえてほしい。

標的艦は下のスクリーンショットの構造をして、反対側を向いて配置する。装甲は初期の鉄鋼。
射撃する塔も同じく下のスクリーンショットの構造である。
キャノン砲を3門構え、時間を最大倍速にした場合、36秒で弾を撃ち尽くす。
実験は各箇所で3回行い、時間を最大倍速にする。塔が弾を撃ち尽くすと勝利になる。
すべての兵装が破壊されると敗北になる。墜落は浮遊機関が破壊され着地することを指す。
1の位置にいる標的艦は平均12秒で敗北するほどのダメージを受けた。
2の位置にいる標的艦は平均19秒で敗北するほどのダメージを受けた。
3の位置にいる標的艦は平均17秒で墜落し、平均32秒で敗北した。3回の内1回勝利。
4の位置にいる標的艦は平均13秒で墜落し、平均34秒で敗北した。3回の内2回勝利。
5の位置にいる標的艦は平均18秒で墜落し、平均33秒で敗北した。3回の内1回勝利。
6の位置にいる標的艦は平均28秒で墜落したが、一度も敗北しなかった。
標的艦と射撃塔の設計 実用性は低い
戦闘について 射撃命令の影響
戦闘中は移動や鹵獲の指示以外に、射撃の種類を命令することができる。
通常射撃の他に精密射撃と速射射撃の3種類が存在している。
次にあげる1例は、3台のキャノン砲が小型弾薬庫(24発分)に隣接する艦が、弾を撃ち尽くす(合計75発)まで標的を射撃したスクリーンショットである。時間は一番早くしている。
与えた損害は確認できた分だけ。破壊に至らないダメージは計算していない。

与えた損害
上空攻撃1 ストラット(支柱)16
梯子付き通路2
ダメージ
80×1+40×16+32×2
装甲の石壁3×80
計 1024ダメージ
.

与えた損害
上空攻撃3 ストラット17 梯子付き通路2 寝室1
ダメージ
80×3+40×17+32×2+42×1
装甲の石壁6×80
計 1506ダメージ
.

与えた損害
上空爆弾1 ストラット6
梯子付き通路2 1炎上
ダメージ
80×1+40×6+32×2
装甲の石壁4×80
計 704ダメージ
.
速射射撃の時間当たりのダメージは他に比べ低いが、他の射撃を含めて反撃されることを計算に入れられていない。早く無力化できるかもしれない速射が結果的にはいい場合もある。
以下標的と射撃艦の設計である。艦は作者がよく使う、一番安い砲艦である。名前はランダム生成。
敵国について
征服モードの主要な敵である他国の行動について箇条書きしておく。
設計面
設計のテンプレートをそれぞれの国家がもっている。
武装の好みがあり、技術レベルや経済力が増しても、概ねその中で強化を繰り返すだけだ。
新しい傾向を取り入れることはない。
建造物
勝敗が防御側の降伏でついた場合、都市に無傷の建造物が残る。
飛行場を作らない国でも降伏の結果として、こちらが攻めたときに登場することがある。
降伏と撤退
降伏は、都市に建造物しか生存していない状態で、圧倒的な戦力差があるときに起こりやすい。
撤退はよくわからない。このゲーム最大のブラックボックスだ。
外交
外交要素は、同盟という名の合併が突然行われるだけしかない。MODで禁止できる。
プレイヤーを特別に敵視するような行動はとらない。狙えるなら全国家から狙う。
諜報
諜報をきちんと行い、建造物への工作や建造の妨害をかなり頻繁にしてくる。
低難易度でも、敵は都市を観察している。勝てると踏まないと基本的に攻めてこない。
敵国だけではないが、侵攻対象は移動を開始した時点で伝わる。遺跡を先に対象にしてから接近すれば駐屯が間に合わないこともある。
侵攻を一瞬でも見せる(すぐに戻っても)と以後の敵国はこちらに対して警戒態勢をとるようになることが多い。艦隊を戻して動かさない。新造を始める。
こちら側も含めて諜報の効果は、都市の現況と収入と建造中の艦船等の進捗確認、破壊工作・妨害工作の前提条件である。費用は開始に100と継続的に5かかる。工作の費用は高額で確実に成功するわけではない。補助的存在と考えた方がいい。
拡大
難易度の上昇によって手堅い行動をとるようになると考えられる。
後のことは気にせず拡大 → 占領後、兵力を駐屯させて建造物を作ってから動く。
攻め込んできても、先に兵力を置くとそれを計算して行動を決める。勝てるとみるとそのまま攻めてくる。無理そうならこちらの部隊が都市に到着した時点で帰る。
中途半端な計算をすることが稀にあり、侵入、戦闘開始、即撤退、帰宅、侵攻の繰り返しという不毛な行動を起こす。(移動がノーコスト、撤退がノーリスクで行えるため)
ただしこちらの妨害(戦略マップで移動中の部隊を戦闘対象に指定すること)に対しては戦力差を気にせず目的地まで向かってくる。
戦闘
建造物の死角をきちんと計算している。適当に作るとそこを突いてくる。
移動する兵器を相手にしていると、自分は撃て、こちらは撃てない場所を目指して動き続ける。
モンスターについて 妨害内容・強さ・報酬
モンスターは初期設定に基づいて、各地に配置される。時間の経過で、空き地に出現することもあり、予兆や条件は不明。全国家の敵であり、交渉や取引の余地はない。
注意点として名前はシナリオ作成モードの設置可能モンスターからの引用と記憶と勝手につけた名前(ごく一部)が混ざっている。征服モードでは出てこないまたは名前が違う場合がある。
(すぐ下の巨大亀はリョコウバトという名前だった気がしてきた)
妨害内容
中立
拠点から動かず、害のないモンスターは少数だがいる。倒しても悪いイベントはない、むしろ金銭か国家ボーナスが得られる。
例は、ストーンガーディアンと巨大亀。(亀は無抵抗・ガーディアンはそこそこ強い)
パッシブ
多くのモンスターは存在するだけで近隣の都市1つの収入を下げる。倒すまで永続する。
最低値は-10と-20が頻出で、最高は-70まで見たことがある。
減少量と強さの関係は複雑で、カルト宗教(-10程度のときと-70の巨大イカを召喚しているときがある)のように変化したり、シェルウォーカー(-10)のような低額でも凶悪な強さを持つモンスターも存在している。

海賊とシェルウォーカーに狙われた都市の図。
海賊の方が低下値は大きいが、戦力はウォーカーの方が圧倒的である。
パッシブのみ
カルト宗教・ムーンディスク・シェルウォーカー・スカイクラーケン・クラーケンレブナント・巨大バチの巣・ジャイアントブラックウィドー・ジャイアントウルフスパイダー・電気クラゲ
アクティブ
近隣都市の収入減少だけでなく、定期的に部隊を派遣し略奪を行ってくる。ターゲットは全世界の都市からランダムで、ブリガンドを除き、自国領土にいても外国へ遠征することは少なくない。
略奪者が都市に到着すると、通常と同じ戦いが始まる。ただし、一定時間の間に撃破できないと都市の収入が20%単位で減少する。戦闘を回避するか、最大時間が経過で、-60%に達する。
この略奪は占領と同じ処理がなされ、時間の経過とともに2段階で回復する。
遠征もあり
マッドサイエンティスト(イカ型ロボ3体or触腕ロボ)・ドラゴン・各種の色ドラゴン・エルダードラゴン(明白に通常より強い)・海賊(飛行艇の略奪者)・海賊王(海賊の強化版)・ブリガンド(地上部隊の略奪者)
各種の色ドラゴンは ホワイト・グリーン・グレーの3種類いる。
強さ
体感および雑な不等号で表現する。
襲撃の強さ
ブリガンド < 海賊 < マッドサイエンティスト
≦ ドラゴン ≦ 海賊王・カラードラゴン < エルダードラゴン
ブリガンドは小さな地上戦艦(装甲車)1台か2台で襲撃最弱。
海賊も少し強いが、小規模な飛行艇の部隊。序盤と防衛設備のない都市以外は乗り切れる。
海賊王は強力な旗艦と2隻程度の中型艦と5隻程度の小型艦を用いてくる。かなり危険だ。
マッドサイエンティストは、イカ型ロボ3機程度や触腕ロボとイカロボの2パターンある。どのロボも乗員を捕食するついでに船や建造物を破壊してくる。テンプレートの防衛設備2つ程度では辛い。
ドラゴンは高速移動の火炎放射。ホワイトは通常と同等、グリーンは通常の少し強化版。グレーは明白に通常ドラゴンより硬く、火ではなく弾を吐き出す。このレベルの敵だと、勝てても防衛設備の修理金額が略奪被害額より大きくなるかもしれない。
エルダードラゴンはドラゴンの改良強化版。大型化、高耐久、火炎放射の射程が長い。
ミッション作成モードを利用したモンスターの近影
人間系の襲撃者の図。中身も見れるが、マッドサイエンティストのユニットは特殊な種類であり、見たところで再現はできない。ただし空中イカと触腕ロボは撃破ボーナスで敵国も含めて製造可能だ。
これらの襲撃は間に合えばインターセプトの指示ができる。地図上でこちらの部隊をクリックして、ユニットにマウスを合わせれば妨害指示になる。迎撃戦は勝利しても艦艇の喪失判定が厳しくなっている。迎撃するか都市で待ち受けるかは慎重に判断したい。
こちらから攻め入るときの難易度(記憶と体感と雑な不等号)
巨大カメ(無力)< 電気クラゲ(最弱)< ブリガンド < 巨大バチの巣 < 巨大グモ
< 海賊 < ストーンガーディアン ≦ クラーケン < カルト宗教
< ホワイトドラゴン < ドラゴン ≦ グリーンドラゴン < グレードラゴン
< 海賊王 < マッドサイエンティスト < シェルウォーカー < エルダードラゴン
< ムーンディスク
注記
人間系は襲撃部隊の他、建造物で抵抗してくる。
ブリガンドは小さい砲台。海賊は中規模な建物。海賊王は装甲と砲台が増設されている。
カルト宗教は建物以外でクラーケンレブナントを召喚している場合があり、強さがピンキリだ。
マッドサイエンティストの拠点は格別に強い。高耐久で誘導・高威力の光弾攻撃をしてくる。
ドラゴン系のモンスターは拠点に巣を作っていて、無害だがターゲットになるため注意を取られる。ドラゴン自体は、3体程度出てくる。エルダーは1体だが護衛の通常ドラゴン数体もいる。
生物系の拠点は、基本的に本人?しかいない。攻撃は捕食が中心。移動が速いため、近づかれないようにはできないが、反転して砲でとらえられるようにしておこう。ハチの巣だけは独特で、硬い空飛ぶ巣からハチが船に乗り込んでくる。
機械系?のストーンガーディアン・シェルウォーカー・ムーンディスクも単独だ。確実な誘導弾で削ってくるものの、能力自体は控えめなガーディアンに比べて、後者2体は非常に危険だ。
足の着いた卵のような、シェルウォーカーは外装が強固であり、攻撃時以外まともにダメージが通らないだろう。その攻撃が非常に強力なビームということもあり苦戦する。被害に見合う報酬を得られるとは限らない。
ムーンディスクは別格の強さがある。極めて耐久力が高く、高高度まで飛べ、ゆっくりと次々に撃ち出してくる爆弾の威力はとんでもない。終盤の艦隊でもかなりの被害を受けるだろう。こいつに挑める場合、征服は消化試合のはずだ。裏ボス的存在。
報酬
モンスターのいる拠点に部隊を送り込み、そこでの戦闘に勝利すると、都市収入のマイナスがなくなるだけでなく、報酬が得られる。ただしクラゲは-がなくなる以外はない場合が多い。
金銭では800から14000。一時金であり、調子に乗って大型艦を作ると維持費で痛い目をみるかもしれない。
記憶をたどる具体例として、ブリガンドは800が多い。海賊は2000程度、海賊王は10000越えもある。マッドサイエンティストで4000から8000、ドラゴンクラス以降だと10000を超えることが多い。ストーンガーディアンも10000を超えたことがある。
ランダム性が強く、期待通りにいかない場合が多い。
人間系だけでなく生物系・機械系の敵問わず撃破報酬には、技術ツリーの進展もある。
選択性の技術の選ばなかった方が手に入ることもある。(研究では不可能な両方取得扱いになる)
特別なボーナス
ドラゴンライダー(高速移動・火炎放射)・メカニカルスカイスクイード(イカ型ロボ・そこそこの高速・足で乗員を直接狙う)・フレッシュクラッカー(地上兵器・イカ腕で攻撃する)というモジュール概念のない特殊なユニット。
アシッドスピッター(強化した火炎放射的武装)・ムーンディスクの破片の入れ物(全モジュール最高の浮遊力が発生)といった特殊なモジュール。
シェルアーマー(木製装甲より少し硬い程度で浮遊力が発生する)・ドラゴンハイド(鉄鋼装甲並みの防御力を持ちながら重さ0)などの特殊な装甲。
これらを解禁するボーナスが、金銭や技術の進展の代わりに、得られる場合もある。
アシッドスピッターを除けば、かなり高価である。
おすすめの戦術
小規模な敵都市への侵攻は、砲撃よりも鹵獲がいい。
ある程度戦力が整うまで、敵地の侵攻は手持ちの部隊でやるほかないが、初期の拡張が終わった後の小規模な都市侵攻は鹵獲艦を設計し、送ることをおすすめする。
(攻撃側の戦力がある程度大きくなると、防御側が少数の小規模建造物だけしかない場合、戦力差の判定によって戦闘開始直後に降伏する。駐留艦隊がいる場合も先に艦を撃破すれば同じ結果になる)
マリーン部屋2つと最低限(寝台とコックピットと帆とダストタンクとハッチ2つ)の設備を持った船で建造費340と維持費は11。小さな建造物ならこれ一隻で制圧可能だ。ただし、それ以外は何もできない。敵の飛行船には勝てない。(高度50メートルも飛べないため鹵獲はほぼ無理)
事故に備えて2隻あれば安心できる。5隻並べれば中規模以下の都市は落とせる。
鹵獲部隊は、木よりも少し上程度の高度以下に船がいる状態で、建造物への移乗命令を出していると、地上に飛び降り、目標へ移動してくれる。(飛べるやつは上空からでも)
その場で命令を出したら、次は後ろに下がってできるだけ弾が当たらないことを祈ろう。離れるほど命中率は落ちる。制圧前に船が落ちると敗北してしまう。
消耗の関係上、1隻が1戦闘で攻撃できる対象はほぼ1つだ。複数の建造物に対応できるよう艦隊を編成しよう。
造船所のない都市は建設にも時間がかかる。鹵獲によって各種の拡張コストを抑えられる。
さすがに大規模な防衛ラインに投入すると、離れていても船が破壊される。小型飛行機で迎撃されたり、火炎放射やノコギリが玄関で待ち受ける建造物も辛い。
その場合は、素直に戦力を整えて侵攻しよう。
急激な拡張よりも防衛を重視する。
都市の取った取られたは、ハイエナを呼び寄せることになる。
都市収入の3分の1は、建造物の維持費に消えてもいい。
守りの硬い都市に敵はわざわざ攻めてこない。
結果的に、何の利益も生まない防衛戦の回数も減る。
複数の建造物を置く代わりに、防衛艦隊(巡回等のコマンドはない。自分の中での役割である)を作る選択も悪くないが、艦隊はピンポンダッシュの繰り返しを誘発させることもある。
モンスターは場所を選ばない。本拠地や重点的に固めた以外の都市にマッドサイエンティスト以上(中盤以降はドラゴン以上)の敵がやってきたときは、修理・再建費用の方が高くつくかもしれないため、略奪を受け入れても構わない。
ズルい技
ここでは仕様の穴をついたかなりズルい技について解説する。多用はゲームの面白さを損なう。
乗っ取り・撤退・即乗っ取り
(Version 1.0.18.1の修正によって仕様が変更された。占領中以外の自国の都市に入りしばらく停止しないと物資や人員は補充されない。よってこの戦術は万能からやや難しいに変わった)
この世界に人的資源や戦略上の補給という概念はない。戦闘が終了すると、無事な部屋の物資や人員は自動的に補充される。
先ほどは大規模な防衛ラインへの鹵獲攻撃を注意したが、ある程度の船を集め、犠牲を許容した場合、攻略は不可能ではない。
手前の建物に全力投球。乗っ取り。他の建造物が攻撃。乗っ取った建物が崩壊。撤退。また侵入。手前の・・・。を繰り返してやると、砲艦を集めるより安上がりに占領できる。
もちろん船舶などの駐屯がある場所では困難だが、運がよければ勝てることもある。
撤退はノーリスク
このゲームの納得のいかない仕様に、無傷の船が撤退するときは、何のリスクも存在しないことが挙げられる。移動のコストが実質ないことと合わせて、ピンポンダッシュ的動作がここかしこで起きる。
まともに立ち向かえない敵の大軍がやってきたときは、移動中の敵部隊を迎撃して一・二隻撃破、やられる前に即撤退を繰り返していくと、何とかできるかもしれない。
都市の建造物や駐留艦隊を無料で確認したいときは、侵入してすぐに撤退を選べばいい。
建物の修理は異次元で
(上記の修正でこの戦術も不可能ではないが難しくなった)
上記した仕様を、建造物の修理がどんなに小さな部分でも、完了まで全体が撤去される仕様とともに合わせると、建物を無視した都市の攻略が可能になる。
少し破壊したのを見てから撤退。時間を止めて、移動指示、少し離れたら再侵攻で、修理完了より先に入ると、その戦闘で修理中の建造物は出てこない。
ちなみにモンスターの拠点でこの戦術は使えない。侵入の度にすべてが再生されるからだ。
おわりに
稚拙なガイドを、ここまで読んでいただきありがとうございます。
楽しいゲームで、日本語訳もあるのに、日本語のガイドがないのはもったいない。
そう思い立ったのが吉日とばかり一気に書き上げた次第です。
Airships: Conquer the Skiesで一番気に入っているところは、大砲の音です。
無駄に大砲を備え付けた船を並べて、戦闘させるためだけに起動したことが何回もあります。
ガイドをまとめるためにプレイしてようやくオーバーレイに気が付きました。
新しい発見が生まれて満足です。
個人的には初めてガイドを公開した時の緊張はもはやなく、恥のかき捨て状態となっております。
最近のゲームは、オンラインで対戦したり協力したりするのがメインストリームですが、この記事
はその傾向へのささやかな抵抗です。
こちらに来てくださった、一人でゲームを遊ぶのが好きなすべての方、制作者や先駆者の方々への
感謝をのこしつつ、終えようと思います。
改めてお付き合いくださり。ありがとうございます。
2020 9と10 制作・公表・誤字と誤記の修正
11 直近のアップデート対応 誤字の修正等 他ゲームガイドの紹介
12 直近のアップデート対応 誤字の修正等
2021 2 アップデートへの簡易対応
3 アップデートへの簡易対応
7 アップデートへの簡易対応
同一作者によるガイドの紹介追加については記載しない。
誤字の修正程度では記載しない。
制作した他ゲームガイドの紹介
規約上許されるのか不明だが、他ゲームの作ったガイドを紹介する。怒られたら消す。
Death Road to Canada
ゾンビローグライク(ト) 翻訳が無理そうなパロディ群 豊富なアイテム 言語を越えた傑作
[link]
Deadly Days
ゾンビローグライク(ト) パーティがどんどん強くなるスピーディな展開と高リプレイ性が待つ
[link]
Sword of the Stars: The Pit
ゾンビが出る純ローグライクゲーム 深い沼 作者が達成した希少実績の大半はこのゲームから
[link]
Ratropolis
スレスパ系の都市防衛 豊富なカード群でデッキを組み換え勝利へ 1周約30分高リプレイ性
[link]
Software Inc.
デジタルテクノロジー会社経営ゲーム 経営だけでなく自由に自社社屋を設計できる要素もあり
[link]
Cannibal Crossing Death Road to Canada制作陣による精神的続編
広いアメリカ縦断から狭い田舎町からの脱出劇へ 前作以上のサバイバルとアクションが楽しめる
[link]