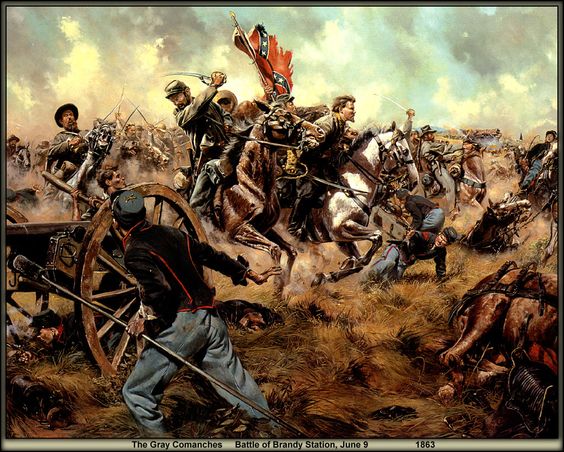Overview
久しぶりにこのゲームをやったらやっぱりクソほど面白かったので思い出しがてらガイドを書いてみることにする とりあえず内政部分まで 気が向いたときにせこせこ工事します
内政編
このゲームのキャンペーン攻略の最も重要な部分。小戦闘ないしは大戦闘の合間合間に戦闘の結果(よほどのことがない限り勝利だとは思うが…)から得られる資金と人的資源を元に先の戦闘の被害を立て直し、軍をさらに強くする。
さてそれぞれの画面について、やれることと見逃しがちな仕様についておさらいしてみよう。
ARMY(軍隊)
内政中一番見ることになる画面だと思う。名前の通り自分の軍隊を組織するためのコマンドがすべてある場所だ。
まず指揮官から見てみよう。指揮官は軍団長、師団長、旅団長の三種類がある。
軍団長は、准将から配置が可能になる。各部隊に具体的な能力の寄与は一切せず、いくつかのパッシブ特殊能力を自分の指揮下の部隊に与える。特殊能力はどれも強力なので各々の好みで自由に編成しよう。
師団長はこのゲームで最も影の薄い存在だろう。軍団長や旅団長のように目に見えて戦場に存在せず、後述するように補正の範囲も少ないからだ。大佐から配置可能で配置された指揮官の階級と経験値に応じて指揮下の部隊のコマンド(命令)能力に補正を与える。別に師団長が大佐だろうとしても指揮下の旅団長は准将以上でも何も問題はない。コマンドは部隊規模に対して低すぎると、エフィシエンシー(効率)能力にマイナス補正を与えるため重要な能力なのだが、師団長が大佐の時点で旅団長が中佐なら歩兵1500、大佐なら2000、准将以上なら2500をなんのマイナス補正なしで指揮できるので気にするときはあまりないだろう。師団長は大佐か中将でよい。中将を師団長に入れていると、指揮下の旅団は旅団長が大佐で2500の歩兵をマイナスなしで指揮できるようになるため価値が出てくる。部隊規模の増加に応じて指揮官が足りなくなってくる中盤以降でたまに役に立つ知識なので覚えておこう。
余談だがこのゲームの日本語はバグなのか前述したマイナス補正の記述が出てこない。(マイナス自体はしっかりされる)気になったら一時的に英語に戻してエフィシエンシーの項をねっとり見るといいだろう。
旅団長も基本は師団長と一緒である。階級と経験値に応じてコマンド能力に補正を与える。師団長より補正の割合が大きいため階級の高い指揮官は旅団にどんどん配置しよう。ちなみに部隊がそれぞれ持つ特殊能力(パーク)は部隊のすべての能力の平均が参照されるので、あとちょっとで星2とか3になる旅団に階級の高い指揮官でコマンド能力を高くすると届いたりするので覚えておこう。
次に兵科に関して見ていこう。このゲームは大きく分けて4つの兵科に分かれている。歩兵・散兵・騎兵・砲兵だ。それぞれの特徴を見ていこう。
歩兵は軍団の中核をなす部隊だ。安く編成できて全兵科中最も打たれ強い。歩兵がいなければ攻めることも守ることもできないだろう。武器は旧式のマスケットとライフルマスケットで火力に大幅な違いが出てくる。全部隊は金が足りなくなるので物理的に不可能だが、星2以上の部隊には必ずライフルを持たせるようにしたい。
散兵はここから持たせる武器でさらに実際の運用に二種類の変化が起きる。1つは連射速度に優れるが射程の短い後装式カービンライフル、もう1つは連射速度に難があるが射程と命中率が優秀な狙撃銃を持った散兵のことだ。説明の便宜上前者を速射散兵、後者を狙撃散兵と呼ぶことにする。速射散兵は戦列の最左翼か最右翼に位置させ、常に敵の側面を取りに行く機動をとるのが基本の使い方になる。狙撃散兵も側面をとるのは一緒だが戦列とともに行動せず、独自に射線の通る場所で撃たせるのが基本になる。ちなみに偵察という散兵の任務の一つは、歩兵から分離させた散兵に行わせるのがよい。散兵の銃は何を買うにしても高級で、不慮の接敵による不本意な損害を受ける可能性のある偵察任務は向いていない。一応スキル等の関係でスポッティング等の能力は分離散兵よりは高いのだが…ちなみに実用上速射散兵は弱く、狙撃散兵は非常に強力だ。なぜなら速射散兵で行うことは歩兵の分離散兵で十分可能であり、そんなものに部隊枠を1つも使う価値はかなり薄いからだ。逆に狙撃散兵は射程という強力な武器を持っている。敵の射程外から一方的に狩る能力というのは貴重である。狙撃散兵の注意点として高難易度だとAIが割と的確に騎兵部隊を差し向けてくるので2~3部隊歩兵の分離散兵を護衛につけておくとよいだろう。
騎兵も武器によって2種類ある。サーベル付きの射程の短い騎兵拳銃と後装式のカービン銃だ。これも前者を衝撃騎兵、後者を竜騎兵と呼ぶことにする。衝撃騎兵は古来より続く由緒正しき騎兵である。突撃時、そして格闘能力が非常に高く、他部隊との連携が取れず孤立した部隊を的確に狩る能力を持っている。逆に正面での戦闘は向いておらず、敵の真正面に突っ込もうものなら大損害を受ける。非常に扱いの難しい兵科だ。なぜかAIはこいつらで射撃戦を行うのだが、プレイヤー的な操作ではかなり精密な操作が要求されるので高級な武器はあまり意味がない。せいぜいコルト銃程度でいいだろう。竜騎兵の特徴はなんといっても下馬ができることである。名の通り馬から降りて戦わせることのできるコマンドで、乗馬状態よりも防御力と装填速度に優れる。敵の戦列側面に素早く回り込んで下馬してからのカービン銃の一斉射撃を叩き込んでやろう。筆者的には竜騎兵を師団単位で編成して乗馬状態のまま運用するのが好きなのだがあまり賛同を得られない。
砲兵は大きく分けて3つある。滑空砲、榴弾砲、ライフル砲の3種類だ。そして弾の種類も3つある。至近距離で使われる散弾(ブドウ弾)、中距離で使われる榴弾、遠距離で使われる実体弾だ。前作と違いそれぞれ目標の距離に応じて自動で切り替わる。滑空砲は命中精度と射程に難がある代わりに散弾の威力が非常に高く、榴弾砲は射程に難がある代わりに榴弾の威力が高く、ライフル砲は威力そのものが低いため近~中距離においては他二つに劣るが射程と命中精度が良い。目に見えてすぐ何人殺した殺されたがわかる他3つの兵科と違って、その強さが分かりづらいと思う。この兵科の最大の特徴は士気へのダメージ能力が非常に高いことだ。効果的に運用してやればあっという間に敵を敗走させることができる。最初は運用の簡単なライフル砲から使ってみよう。数個旅団で集中砲火するだけで目に見えて敵の崩れやすさが変わるはずだ。慣れてきたら榴弾砲も使ってみよう。どんな距離でもほぼ変わらない火力を発揮してくれるライフル砲と違い、実体弾の距離だと大幅に威力が減衰するので、常に榴弾が打てる距離を気にする必要があるが、威力はライフル砲以上だ。滑空砲はまず使うことはないと思う。効果的な運用ができる場面が非常に少なく、また砲自体もそんなに強くない。ただ散弾の威力に関してだけはかなり良いので射撃禁止コマンドをうまく使ってやればかなりの破壊力を発揮する。
パーク
ARMY(軍隊)の項目に一緒に書こうと思ったが、探しやすさのために別にする。始めたばかりの人にはピンとこないかもしれないが要するに部隊の星に応じて取ることのできる能力のことだ。部隊の平均能力によって星は判定されており(星1から30、50、70だったはず)兵科によって能力もそれぞれ違う。一つ一つ見ていこう。
歩兵星1パーク、規律訓練と持久力訓練。
規律訓練は名の通り士気防御力に補正を与える。割と馬鹿にならない補正で星1の新兵に毛が生えた部隊が士気の仕様も相まって(戦闘の項で詳しく解説予定)しっかり前線を支えることのできる部隊に早変わりする。
持久力訓練は名の通りスタミナに補正を与える。スタミナは部隊の速度にかかわるのであって損はないが違いは分かりづらい。
ここまで書くと規律一択の気がするが、士気能力は相手の攻撃を受けると上がる項目で割とすぐ育つ。星1だろうと一回戦闘を経ると70や60まで育っていたりする。逆にスタミナは戦場を移動した距離で上がるのでなかなか上がりづらい。
要するに短期的に見れば規律。長期的に見れば持久力が良い。状況に応じて取る方を考えよう。
歩兵星2パーク、強襲訓練、銃器訓練、狙撃訓練
強襲訓練は格闘戦に関する項目が一通り上がる。銃器訓練は命中率が下がる代わりに装填速度が上がり、狙撃訓練はその逆。
まず強襲訓練はとることのない項目だろう。星2の歩兵部隊ともなれば部隊の中核を担う精鋭部隊であり、そんな精鋭を他2つの能力を押しのけてとるのが良いと思うような乱戦区域に常に投入することは戦術の敗北だ。ここまで書いたが別に悪いというほどではない。のだが他二つのほうが強いというのが正確なところだ。
銃器訓練は星2能力の中で最も優秀な能力だと思う。戦闘の仕様上戦列射撃を多く行ったほうが結果的に被害も少なくなる。欠点としては弾薬消費が激しくなるため継戦能力は落ちることだろう。
狙撃訓練は操作量の低減能力だ。弾持ちがよくなるため補給部隊を回すのを少し忘れていても弾切れを起こしづらいのが良いところだ。
筆者的には銃器訓練一択なのだが正直どれも強い。プレイスタイルに応じて取る能力は個々人で決めてよいと思う。
歩兵星3パーク、エリート、狙撃兵
歩兵の仕様上星3の維持はべらぼうな金がかかるのであまり気にしたことはないかもしれない。筆者も気にしない、製作者も分かっているのか特殊能力もテキトウだ。
エリートはなんかいろいろ上がる。狙撃兵はスポッテング以外は銃関連の項目があがる。
基本狙撃兵でいい。ここまで来たらほぼすべての能力がマックスまで上がっており、補正をかける意味は薄い。スポット能力は上がるだけ得なのでとるならばこっちだろう。
散兵星1パーク、規律、持久力訓練、銃器訓練
散兵の第一パークは歩兵に毛が生えたような内容だ。割と悩む歩兵のパークと違って持久力一択だろう。
規律はそもそも規律が働くような正面からの打ち合いは散兵は行ってはいけないし、銃器訓練もうま味は薄い。
散兵の運用上軍団を離れて戦うので弾持ちの悪くなる銃器訓練は結果的に火力が減るからだ。
散兵星2パーク、偵察訓練、狙撃訓練
割と悩む内容。筆者は偵察をいつも取っているが狙撃も悪くはない。
ARMY(軍隊)の項目では専門職としての散兵は偵察任務に向いていないと書いたが、これは偵察のためではなく相手に一方的にスポットされないようにするためだ。
AIの散兵とのスポット合戦で不利に働いてしまうのを嫌っている。スタミナが上がるのも良い。
狙撃は狙撃で強い。散兵の運用上装填速度が下がるのは特に気にする要素ではない。
散兵星3パーク 偵察兵 狙撃兵
星2パークでとった方をそのまま取ろう。このゲームに限らないが長所をそのまま伸ばすのが強いからだ。
砲兵星1パーク、兵站、身体訓練、規律。
兵站は昔のバージョンだとバグで弾薬上昇の効果がなかったが現在は修正されている。
身体訓練は名前は違うが、持久力訓練と同じだ。
操作性を上げるなら兵站、そうでないなら身体訓練だろう。規律は散兵と同じ理由でとる必要はない。
砲兵星2パーク、戦術訓練、砲術訓練、射撃訓練
戦術訓練の援護射撃は英文だと「cover」要するに戦場での遮蔽率に補正がかかる。
戦術はちょっと特殊で戦場での旋回速度や隠蔽能力にかかる。
砲術や射撃は砲兵の銃器、狙撃訓練枠だ。
おそらくメタ的には滑空砲が戦術訓練、榴弾砲が砲術訓練、ライフル砲が射撃訓練として用意されていると思う。
大体これで合っているが、なるべく前で運用したい榴弾砲の運用上、戦術訓練のほうが良いと思われる。ステルスが上がるのが割と馬鹿にできない。
砲兵星3パーク、短距離射撃訓練、長距離射撃訓練
これのせいで砲兵は星3かそれ未満かで倍ぐらい強さが変わる。
短距離射撃訓練はキャニスター弾、つまり散弾の威力が上がり、長距離は榴弾と実体弾のダメージが上がる。
言うまでもないが榴弾砲が前者、ライフル砲が後者だ。
砲兵はその仕様上まともにやると星3部隊を作ることが難しいので(星は部隊の平均能力値を参照するのに格闘値が全然上げられない)
その他の項目に記したベテラン錬人術を使うと楽に編成できる。
騎兵星1パーク、規律訓練、騎行、持久力訓練
騎兵の持久力訓練は歩行速度に補正がかかるので注意。
騎馬状態の移動速度が上がる騎行が頭一つ抜けて強いだろうか。
衝撃騎兵として育てるならスタミナに補正がかかる持久力訓練も悪くはない。
騎兵星2パーク、騎兵訓練、射撃訓練、偵察訓練
騎兵訓練は格闘能力、射撃訓練は射撃能力、偵察訓練はスポット能力が上がる。
衝撃騎兵なら騎兵訓練一択。竜騎兵なら他二つをお好みでという感じだ。
騎兵星3パーク、衝撃騎兵、乗馬歩兵
まんまである。
今まで育ててきた騎兵の特徴に応じてあっているほうを選ぼう。
軍団長
准将パーク、戦略、戦術、教官
戦略は部隊の弾薬量増加。戦術は移動速度、教官は経験値が増加する。
操作性を追求するなら戦略。速度は何よりも必要な要素だが、部隊の練度維持、向上に大きく貢献する教官も捨てがたい。
もはや好みの領域。教官にやや軍配が上がるだろうか。
少将パーク、砲兵、歩兵、騎兵
注意するのは准将パークと違い、それぞれ対応する兵科にしか補正がかからないところだ。
そのため基本は歩兵でいい。
複数の軍団が投入できるようになる終盤の大戦闘では砲兵が大部分を占める軍団を作り、砲兵パークをとるのも悪くない。
騎兵はややネタ感が強い。
中将パーク、リーダー、攻撃兵、防衛兵
どうも戦場で軍団長の円内にいるときに補正をかけるらしい。そんなわけで操作性の向上するリーダーが良い…のだがどうもバグで軍団長の円は大きくならずに補給車の円が大きくなる事例が報告されている。
最新のバージョンでも確認したので直っていない。まぁそれはそれで操作性は上がるからいいのか?
効果範囲が狭いのであまり気にする要素ではない。
ARMORY(武器庫)
歩兵銃、散兵銃、騎兵銃、大砲を直接買えるショップ。自分の持っている銃を売ることもできる。低難易度だとアーミーで部隊を補充するときに一緒に不足分の武器を買ってくれる便利仕様のため、資金不足の際に型落ちの武器や鹵獲武器を売る以外でここを使ったことがないプレイヤーも多いかもしれない。なんでわざわざここで武器を買う必要があるの?って言うと実はこのゲーム大戦闘ごとにショップの内容がリセットされる仕組みなのだ。
つまりある時に買わなかった武器類はその時の大戦闘が終わると追加されずに破棄され新しくなる。スプリングフィールドシリーズのような通常の歩兵銃ならあまり気にすることはないと思うが、常に在庫があまりない高級な銃で部隊を編成しようとしたときこの仕様を知らないとちょっともったいなかったりする。あまり在庫のない高級銃や大砲は大戦闘の前にちゃんと買い占めておこう。
武器解説
このゲームの武器についてざっと解説していく。
歩兵銃
ファーマー
安い・多い・弱いを地で行く農民銃。南軍でのみ購入可能であり、安く部隊を編成するのに最も適した銃だろう。
リボアードファーマー
これも南軍でのみ購入可能。ちょっと性能が良くなった農民銃。値段も上昇しており、ほんの少し足すと、スプリングフィールドというまともなマスケットが買えるため購入する意味は皆無。安いのが取り柄の銃から、安さを取り去ったらどうなるかはもはや言うまでもない。
スプリングフィールドM1842
ここからまともな性能の銃。というかこれが下限。このゲームにおいて射程は非常に重要で、射程が長ければ長いほど命中精度も上がる。どうも最大射程から現在の戦闘距離に対して近ければ近いほど命中精度に補正がかかるようであり、マスケットとライフルマスケットはこの仕様のせいで実数値以上の差が出てくる。なのでできればすべての部隊は最低でもこれを持たせておきたい。
パルメットM1842
説明では命中精度が上がったと書いてあるが微増程度。それよりも格闘値の上昇が素晴らしいので、こちらに注目できるならば買ってよいだろう。スプリングフィールドM1842でも書いた通り、命中精度は距離の要素が大きすぎるので正直射撃戦に関してはほぼ一緒。
M1841ミシシッピ
ここからライフルマスケット銃。旧式のマスケットを装備した部隊を一方的に狩り殺すことができる。これを装備した部隊を始めて運用したとき、その火力の違いに驚いたプレイヤーも多いのではないだろうか。お値段がお手頃なのもいい。序盤にちょっと無理をして買いたい歩兵銃だ。
MJ&G タイプⅡ
南軍でのみ購入可能なライフルマスケット。性能はよいが値段がそろそろ2500人に行きわたらせるには家計を圧迫し始める。ミシシッピ銃より射程が20長いのでできればこっちを使いたいが、大体不可能なので買うことはあまりない。
ローレンツ
射程340シリーズで最も安い銃。ここからさらに一段階性能が上昇する。北軍、南軍キャンペーンどちらでも出てきたら序盤の終わりぐらいに少し無理をしても買いたい銃。
タイラーテキサス銃
南軍でのみ購入可能。費用対効果に優れると書いてあるが実際問題として命中がやや低いので微妙。北軍キャンペーンの中盤で鹵獲兵器としてよく見かける。
1853エンフィールド銃
ローレンツとそう変わらない性能のように見えるがリロード時間がかなり改善されているので使い勝手はかなりいい。
スプリングフィールドM1855
エンフィールドとほぼ変わらない性能。ただショップの数がかなり多いので結局こっちを買うことになる。微妙な違いとしてはこっちのほうが一斉射の威力がやや低い代わりに装填時間に優れる。
ハーパーズ・フェリーM1855
スプリングフィールドM1855より射程が10も長い。南軍キャンペーンの中盤で鹵獲兵器でよく見かける。
CSリッチモンド
史実ではスプリングフィールドを勝手にパクって生産した粗悪品…なのだがどういうわけか結構性能がいい。南軍キャンペーンで買える最も性能がいい量産ライフルマスケット。ライフルマスケットの中ではかなりの格闘能力を誇るので防御面でも優秀。
スプリングフィールドM1861
北軍キャンペーンでのみ購入可能。ここまでくると一斉射で敵が敗走することも珍しくない。最精鋭部隊に必ず持たせよう。南軍キャンペーンだと最高難易度の鹵獲兵器で見かけることができる。
スプリングフィールドM1863
1861と比べてやや命中精度が上昇。北軍では少しでもM1861の配備を急がせるためにあまり買わず、最高難度の南軍キャンペーンで逆によく使う銃
コルトモデル1855
ここから非量産高級銃枠。北軍でのみ購入可能。高い発射レートを持つ。射程が短すぎるため見た目ほど強くはない。正直趣味の領域。
ヘンリー銃
高いだけのゴミ。当時の北軍に正式採用されなかった理由がよくわかる。コルト銃と比べてダメージ値が低すぎるため値段に対してろくな戦果が出ない。
フェイエットビル銃
南軍で購入可能な唯一射程が400あるライフル。高い、強い、少ないを地で行く。でもこれを1丁買うのにリッチモンドライフルが3丁買えるので大真面目に攻略するなら買う必要はない。でもかっこいいから筆者は買っちゃう。
スペンサー銃
速射銃の中で最もまともな性能。さすがにここまでくると強いのだが…一丁でM1861を3丁買えてしまうのでやはり趣味の領域。
総括すると高級銃はコスパが悪く攻略という観点から非常にそぐわない。でもかっこいいから配備してしまうよね
散兵銃
騎兵と共有の銃が多いのでここ特有ののみ解説する
ハンター銃
猟銃、このゲームアタックムーブの指示が最大射程で撃たず、めいっぱい有効射程内に入って撃とうとするので実際は射程-100ぐらいで運用される。銃の解説に戻ると射程が長いだけで装填速度と命中率がクソで、単発の威力が高いので、ゼロ距離で撃つのが強い銃。要するに狙撃銃としてはゴミ。
コルトM1855
射程が短すぎて火力が出ないゴミ。
シャープス銃
優秀なライフル。願わくば歩兵銃として欲しかった。
スペンサー銃
歩兵の項と同上
ホイットワース銃
射程も500まで伸びるとかなり戦術的な運用の幅が出てくる。ただこれをわざわざ買うなら後述する最高級狙撃銃を買ったほうがいい。
ホイットワース(TS)
ホイットワース銃にスコープをつけたもの。南軍キャペーン専用。驚異の射程600を誇る。これを持った最大規模の部隊を常に1つ保持させておきたい。
JFブラウン(TS)
北軍のホイットワース(TS)枠。命中率が多少高い代わりに0.5もダメージが低いせいなのか南軍よりも編成したいと思える戦果が出ない。
騎兵銃
ソード・オフ・ショットガン
南軍限定。驚異の威力25を誇る。射程が短いのでふとしたら格闘戦になるのに注意。
クック&ブラザー
装填が遅すぎるので買う意味はない。下痢便みたいな色をしているがこいつ自身下痢便並みの価値しかない。
パルメットM1842
一番安いサーベル付き騎兵銃。衝撃騎兵は最も損耗が激しい兵科なので新兵のうちから高い銃を持たせても意味はない。なので結構後半までお世話になったりする。
シャープスモデル1855
おそらく竜騎兵用の銃の中で最もコストパフォーマンスに優れる銃。というか南軍ではこれよりパフォーマンスが優秀な銃は1861エンフィールドぐらいだし、北軍でもこれの完全上位互換の1859モデルやスミスぐらいしかない。優秀な装填速度と最低限の射程、そこそこ高いダメージ値と文句なしの銃。数が多いのもグー。
コルトM1855
ARMY(軍隊)の騎兵の部分でも書いたが衝撃騎兵はプレイヤー的な操作ではほとんど能動的に撃つことはできない。ので無理して高い銃を配備してもあまり戦果は変わらなかったりするのでここが上限になりがち。
レミントンM1861
北軍専用、可もなく不可もないので正直書くことがない。
パターン1861エンフィールド
装填にやや難があるが射程が300もあればかなり戦術的な運用の幅が出てくる。騎兵の速度を生かして側面に回り込んで下馬射撃させてもよし、乗馬状態のまま歩兵隊の支援に回してもよし。
昔は北軍でも買えた気がするのだが買えなくなっている。
スミス
北軍専用、高い装填速度と高い命中率、精鋭竜騎兵隊には必ず持たせたい。
1862CSリッチモンド
南軍専用、リッチモンドライフルのカービン版。ダメージ値は12.5と高いものの総合的には値段に見合わない。
シャープスモデル1859
北軍専用、非常に優秀なライフル。あるだけ買いたい。
フランクウェッソン
北軍専用、装填遅すぎ、ダメージ低すぎ、端的に言ってゴミ。高価な分クックよりも質が悪い。
メイナード
悪くはないけど値段が高い。
バーンサイド
メイナードに同じ
スペンサーカービン
北軍専用、最強の騎兵銃。すさまじい速度で射撃が行われ、すさまじい速度で敵が倒れ、すさまじい速度で弾薬がなくなっていく。この銃を持った精鋭騎兵の補給維持のために補給部隊を常に随伴させる必要があるが、それだけの価値は確実にある。南軍でも最高難易度なら敵から奪って編成も可能。
レ・マット・リボルバー
南軍専用、カタログスペックは優秀なように見えるのだが、前述の衝撃騎兵の関係上高いバットに過ぎない。
砲兵
6ポンド フィールドガン
最も安い滑空砲。安かろう悪かろうな砲
6ポンドウィアード砲
身もふたもないことを言ってしまうと6ポンド程度の小口径砲では何を使おうとあまり変わらない。
12ポンド榴弾砲
ここからやっと威力が目に見えて変わってくる。榴弾砲なので戦闘距離には注意。
12ポンドナポレオン砲
フランス大陸軍の主力火砲であり、南北戦争でも両軍合わせて最も使われた大砲。コストパフォーマンスに非常に優れる。滑空砲という特性と武器庫の数も相まって歩兵とほぼ同じ場所で撃っていればいいので運用もむしろ楽。
10ポンド砲
砲兵の運用に慣れないうちはライフル砲を使うのが無難。この砲自体も無難な性能。
10ポンドパロット砲
値段がちょっと高くなり、性能も相応に高くなった砲。
10ポンドドレデガー砲
非常に高い命中性能を誇るはずなのだがあまり違いを感じられない。別に弱いわけではないので十分買う価値はある。
12ポンド ホイットワース砲
射程が非常に長いので使いやすい。
14ポンド ジェームズ砲
値段相応の性能。特に書くことはない。強いて言うなら射程がやや短いので置いてきぼりに注意。
24ポンド榴弾砲
大口径榴弾砲。適切な距離で運用した星3砲兵ならすさまじい勢いで敵を退却させていく。
20ポンド パロット砲
どんな距離でもすさまじい火力を提供してくれる優秀な火砲
BARRACKS(兵舎)
将軍を買う場所。将軍は編成の内政を凝りだすと割と足りなくなる。ここも武器の例にもれずリセットが入るので准将以上は必ず買うようにしよう。
CAREER(キャリア)
いろんな称号や過去の戦いの結果、そして内政的には小戦闘、大戦闘ごとにもらえるボーナスポイントで特殊なボーナスを得ることができる。
ボーナスポイントは以下の7種類である。
POLITICS(政治)
ECONOMY(経済)
MEDICINE(医療)
TRANING(訓練)
ARMY ORGANIZATION(部隊規模)
LOGITICS(補給)
RECONNAISSANCE(偵察)
各項目はゲーム内でカーソルを合わせれば解説されるので割愛するとして、最優先で上げたいのは政治・医療、そして部隊規模の7までである。まず政治は戦闘ごとの報酬…特に人員にもかかるため最優先である。このゲーム金がなくても何とかなることは多いが人がいないとどうしようもなくなる。医療も無料でベテラン兵士が最大20%戻ってくるのは大きい。部隊の練度維持は攻略する上での重要項目の一つだからである。部隊規模の7というのは7レベルで歩兵部隊の規模が最大2500まで増えるからだ。部隊規模が大きくなればなるほど移動・旋回速度の低下・人員ダメージの増加という欠点が出てくるが、それ以上に攻撃力の増加、士気防御力の増加は大きい。逆に部隊規模は8以上は後半からでよい。
そして他の項目であるが、次の優先は経済と補給だろうか、直接的に資金にかかる経済と操作性が向上する補給は上げておいて損はない。訓練は最後、偵察は上げなくてよい。ベテラン補充は資金がかかりすぎるので編成を合理化していくとまず使わないし、使うとしても部隊練度の星を落とさないための調整として数十人単位でしか補充しない。何よりレベル10まで上げても25%の割引しか受けられない。もうないと思うが大幅な仕様変更でレベルごとに5%の割引がつくのならば価値はぐっと上がるのだが…。偵察はフレーバー的なものでしかないので、本当に割り振ることがなくなったならここに振ろう。ここに振ろうが振るまいが敵軍の規模は変わらないし、こっちは強くならないし、何よりやることは一緒だからである。そもそも実際の戦いにおいて、偵察とはどこを戦場に選ぶかの意思決定に大きな影響を及ぼす項目なのであって、初めから戦場が決められているこのゲームではその意味は皆無に等しい。開発が作らないといったので望みは皆無だがトータルウォー式のマルチのようなものが実装されれば日の目を浴びる項目だと思う。
その他
・ベテラン補充のまとめ
1.キャンプのベテラン補充であるが基本的に補充対象の部隊の能力のみで価格が設定されている(リザーブの能力は一切関係がない)
2.同能力のベテランであっても兵科によって費用が違う(歩兵<散兵<砲兵<騎兵)細かい係数は自分で調べて
3.下記のベテラン錬人術において気を付けておくとだいぶ安く補充ができるだろう
・ベテラン錬人術のまとめ
ベテラン錬人術とは
1.旅団は解散するとリザーブに行き現在の新兵に合流しその平均が新兵の能力値として産出される(現在の新兵の練度はキャンプ画面右上の予備役数にカーソルを合わせるとわかる)
2.それを利用してリザーブを0にして優秀な歩兵部隊をそのまま精鋭砲兵に転換する等という小技が可能
3.そしてこれを応用したのが北軍・南軍キャンペーン序盤で手に入る星3部隊(北軍:鉄旅団 南軍:フォレスト将軍の騎兵)でなんやかんやして序盤で最精鋭部隊、特に仕様上編成が困難な星3砲兵・騎兵・散兵を編成するのがこの小技の今のところ実用的な使い道である。
筆者の軍隊編成
要望があったのでさっと書く。
師団単位で兵科をそろえている。操作性の関係上何かと楽だからだ。
基本は砲兵1師団、歩兵2師団、騎兵1師団で編成している。そうでないなら砲兵1~2師団、歩兵3~2師団だ。

軍団長のパークはそこまで気にしていない。基本歩兵パークをとり、最終作戦で砲兵のみの軍団を組織するときだけ砲兵パークをとっているという感じだ。
サプライ増殖
サプライ増殖とは本来1軍団35000が限界であるサプライを限界突破する技である。
やり方は簡単で、キャンプが挟まる大戦闘でサプライ残量が0になっていない自軍の補給ユニットを、マップ外に退却させることで戦闘終了後のキャンプ画面で限界突破する。
やりまくるとこのようになる。
おそらく後述する補給の仕様。(戦闘後資金を使わずに自動回復する)とマップ外退却の仕様(戦闘終了時に戻ってくる)で処理上スタックした補給隊が合わさって限界突破してしまうのだと思われる。
発見者:紹運氏(非筆者)↓ここから紹運氏の文章
☆サプライ増殖のやり方(例:北軍シャイロー)
0.サプライを1以上配置してシャイロー戦を始める(最大値の35000配置は必要ない)
1.シャイロー教会のフェイズとダブル畑のフェイズを戦うなり即被占領カットするなりして終える
2.ホーネッツネストのフェイズでサプライワゴン(以下SW)が出現する
3.ホーネッツネストのフェイズ、または次のピッツバーグランディングのフェイズで『emptyになる前』にSWを戦場から撤退させる
4,一日目のピッツバーグランディング防衛を無事に終える
5.二日目に入る前にキャンプに行けるので行くと、軍団のサプライが『2500』になっていれば成功(また、この時点において2500からサプライを上下させても差し支えない)
7.二日目の戦闘を普通に終える
8.キャンプで確認すると軍団のサプライが『開戦前の値 + 中間キャンプでの値』まで回復しており、最大70000まで増やせるようになり、その軍団を戦闘に出したときSWが二つ出るようになる
※増殖成功時の中間キャンプのサプライは必ずしも2500とは限らない
南軍シャイローや北軍コールドハーバー初日では0、また中途半端な一桁から三桁の数字になることもあった
※いったんこの状態になるとゲーム終了までそのままになり、70000から105000、105000から150000とさらなる増殖も可能で、SWの個数も増えていく
☆増殖による利益
・多くのサプライの持ち込みが可能になり、砲兵の弾薬が尽きにくくなる
・一軍団で複数のSWが使え、操作性に寄与する場合がある(最大サプライ70000の状態でSW二個、サプライ35000以下でもSW個数は変わらず、たとえば20000の持ち込みなら、10000ずつで分割された二個のSWを用いる状態になる)
・下の「サプライ払い戻し」を利用した金策の規模が上昇する
☆増殖による不利益
ユニットを手動で配置できず初期軍・増援が自動で配置されていくステージでは、配置ユニット数が規定されている
たとえば北軍アンティータムのサンクンロード攻撃フェイズでは、右翼攻撃軍団の6戦闘ユニット+SWの合計7ユニットが登場する
ここで注意すべきは、登場する総ユニット数の指定にSWが含まれる点
たとえば上記の軍団のSWが増殖していて3つある状態では、本来なら6+1のところが4+3となって、肝心の戦闘ユニットの配置が阻害されてしまう
この不利益を避けるためには、増殖を行った軍団の運用を工夫することが必要となる
増殖を行った軍団は戦闘開始前にユニットの手動配置があるところで運用するか、そもそも戦闘に参加させないことが好ましいだろう
☆サプライ払い戻し(換金技)
サプライは各ステージ終了時に必ず開始時の状態に自動回復する(この際に資金を消費しない)
これは戦闘中に消費したサプライのみならず、途中でキャンプが挟まる戦闘でサプライを換金した場合にも適用される
またステージに配置していない軍団でもサプライの回復処理は行われるため、組織10なら全5軍団で払い戻しを行える
上の増殖と合わせると、終盤のステージで何十万という大金を儲けることができる
☆増殖&払い戻し可能ステージ
増殖の前提条件は、
1.キャンプが挟まるステージであること
2.キャンプ直前の戦闘で自軍団のSWが配置されていること
複数の軍団の複数のSWが出現する戦闘では、出現するSWの数だけ増殖が可能
ゲティスバーグを代表例に複数回のキャンプが挟まるステージでは、キャンプの数だけ増殖が可能
一方で払い戻しは、キャンプが挟まるステージであれば必ず実行可能だがステージを通して一度しかできない
南北シャイロー キャンプ1回
北軍セカンドブルラン キャンプ2回だが、内1回はSW配置されず
南軍セカンドブルラン キャンプ2回
南北フレデリックスバーグ キャンプ1回
南北ストーンズリバー キャンプ1回
南北チャンセラーズヴィル キャンプ3回
南北ゲティスバーグ キャンプ5回
北軍チカマウガ キャンプ2回だが、内1回はSW配置されず
南軍チカマウガ キャンプ2回
南北コールドハーバー キャンプ4回
☆増殖&払い戻し活用例について
この二つのグリッチによる利益を最大化するためには、増殖できる機会では欠かさず増殖し、払い戻しできる機会で満額を戻すことが必要となる
ただしそれを目指そうとすると、できるだけキャンプを通過する、すなわち戦闘を長引かせる必要が出てくる
戦闘の長期化はもっぱら人的資源を損耗させ、金策で埋めきれないほどの不利益をもたらす可能性がある
たとえば南軍のチャンセラーズヴィルやゲティスバーグは、早期に決着しないと敵軍がワラワラ湧いてきて自軍の損害が肥大していく
また、払い戻しを満額で行うと必然的にサプライが配置されないから、敵から奪ってきたサプライで賄うアテが無いと弾薬切れに苦しむ可能性がある
南北両軍のストーンズリバーやチカマウガのように長期戦が不可避のステージでの満額払い戻しは自殺行為に等しい
加えて、そもそも払い戻しには種銭が必要であり、貧乏すぎるとそれが用意できない点にも注意
よって、現実的に増殖&払い戻しが使える機会は限られてくる
以下においては、筆者がキャンペーンを回した上での南北両軍における使用例を示している
☆北軍活用例
ただでさえ金持ちな北軍は、増殖で100万を超える利益を得るのも難しくない
ぶっちゃけここまでせずとも割と楽にレジェンダリーをクリアできてしまうのが北軍パワーだが、トンデモ精鋭軍をリッチモンドに持ち込んで大暴れしたい人は活用しても良いだろう
・シャイロー キャンプ1増殖2軍団 払い戻し△
最終的に自軍団以外の味方がSWを持ってきてくれる上、敵からも奪いやすいので余裕はあるが、まだ序盤なので満額払い戻しの種銭を用意しにくい
・セカンドブルラン 増殖なし 払い戻し◎
最初の戦闘ではSWが配置されず増殖できない
早期決着を目指さないと南軍が集まってきて面倒なので、増殖を目指さないほうが得だろう
早期決着なら戦闘自体は楽なので満額を払い戻せ、シャイローで二軍団増殖した上で組織10なら245000の利益になる
・フレデリックスバーグ キャンプ1増殖1軍団 払い戻し◎
最初の戦闘は完全な消化試合なので増殖
移動中心で射撃戦になりにくいので満額払い戻しの余裕があるが、キャンプ一回のみでは増殖に用いた軍団での払い戻しができないためセカンドブルランより利益が減る
・ストーンズリバー キャンプ1増殖3軍団 払い戻し△
段階的にSWが出てくるので段階的に退却させて増殖させると良い
3軍団の増殖を狙うならフレデリックスバーグより利益は減る上、射撃戦になりやすく弾薬の余裕も無い
・チャンセラーズヴィル キャンプ1増殖1軍団 キャンプ2増殖3軍団 キャンプ3増殖3軍団 払い戻し○
ここから複数キャンプでの多段階増殖が可能、初日での決着は厳しい一方で長期戦が行いやすいので最終日まで粘って良いと思う
戦場のど真ん中に固定のサプライスポットがあり弾薬のアテがあるのも良い
・ゲティスバーグ キャンプ1増殖1軍団 キャンプ2増殖1軍団 キャンプ3増殖2軍団 キャンプ4増殖1軍団 キャンプ5増殖3軍団 払い戻し◎
怒涛のキャンプ祭り、比較的に楽なステージなので気軽に増殖しまくれる
最終的に「左を補強」に入る軍団以外の4軍団が増殖対象となるが、多数のキャンプで増殖と払い戻しのタイミングをズラせる都合で、最初に増殖する「早朝の増援」以外の4軍団で満額払い戻しが可能
・チカマウガ 増殖なし 払い戻し○
最初の戦闘ではSWが配置されず増殖できない
三日目に進むこともできるが終盤の増殖の利益はさほどではないので、二日目に全VP占拠で勝っておくほうが楽
全日を通して2軍団しか配置されないので、残り3軍団では満額受け取れる
・コールドハーバー キャンプ1増殖なし キャンプ2増殖1 払い戻し◎
初動の「左翼」で増殖できるが、ここに至っては補給禁止で温存して満額払い戻しするほうが得だろう
次の「右翼」はキャンプで1000だけ残し払い戻しておくことで、増殖と払い戻しを事実上として両立できるが、ここまで来たらわざわざ増殖する必要性も低い
最大4回のキャンプが可能だが、もう増殖しても仕方ないしクソデカMAPの戦闘が面倒なので三日目で勝って終わって良いだろう
これまでの活用例に従っていれば、ここでの払い戻しだけで875000の利益が出る計算になる
☆南軍活用例
まずもって南軍は貧乏であり、払い戻しの種銭を確保するためにヒーヒー言わざるを得ない場面が多い
また南軍は大部分のステージで早期決着を目指さないと厳しいため、増殖の機会も北軍に比べて著しく制約される
こんなグリッチにまで南北格差が現れるなんて酷い話だ
・シャイロー 増殖なし 払い戻し△
二日目に入ると大量の北軍がピッツバーグランディングに詰まり、いかに盾役の味方が居てもきついので増殖は諦めた
組織5以上なら3軍団つくれるので、戦闘に参加する1軍団を除いて払い戻しするのも良いが、いかんせん種銭が厳しく中途半端な額がせいぜい
・セカンドブルラン キャンプ1増殖1軍団 キャンプ2増殖2軍団 払い戻し◎
南軍にとって貴重なボーナスステージ
この時点で組織10で5軍団体制、または組織8or9で4軍団体制で、初動の増殖に用いる軍団以外を換金すれば良い
組織10まで上げるのもそれに対応する種銭を用意するのも辛いので、4-1=3軍団相当の35000*3=105000が無難だろう
・フレデリックスバーグ キャンプ1増殖1軍団 払い戻し◎
南軍にとって貴重なボーナスステージ
最初のしょうもない戦闘にSWが配置されることに情けを感じる
・ストーンズリバー キャンプ1増殖3軍団 払い戻し○
二日目になっても北軍の数が増えるわけではないからじっくり戦って良い
どれだけ払い戻すかは弾薬との相談になる
・チャンセラーズヴィル 増殖なし 払い戻し×
初日で決着しないと大変なことになるので、増殖も払い戻しも諦めざるを得ない
・ゲティスバーグ キャンプ1増殖2軍団 キャンプ2増殖1軍団 払い戻し○
損害と増殖のバランスを考えると、二度目のキャンプまで挟むのが丁度良さそう
射撃戦を控えれば、最初に増殖する2軍団以外で満額の払い戻しが容易
・チカマウガ キャンプ1増殖1軍団 払い戻し○
全日を通して戦闘に参加しない3軍団のほうでしっかり払い戻しておきたい
三日目に引き延ばせば増殖の機会も増えるが、わりと今更感が否めないので二日目で終えるのが無難だろう
・コールドハーバー 払い戻し◎
この期に及んで増殖を行う必要性は無いだろうから、払い戻しに全振りしてさっさと終える
☆その他
増殖&払い戻しを用いる際には、軍団のサプライを上下する操作を多用することになるが、1000ずつの上下しかできないため操作性が悪い
クリック連打のために指を動かすのは辛いので、連打ツールを導入しておくのがオススメ
一応、既出の英語情報があるにはあるが、ほとんど研究されていなかったようだ
[link]
↑ここまで紹運氏の文章
戦闘編
このゲームの最も面白い部分。卑劣なヤンキーから祖国を守るのか、身の程知らずの反乱軍に社会の仕組みを叩き込むのかは人次第だが、ここで勝てなければ陣営は文字通り滅ぶ。初歩的な操作は分かっているものとして忘れがちな仕様や気づかない部分、また戦術論にも少しだけ突っ込んで解説しようと思う。
基本的な操作
・基本的な操作
ctrl長押し+左クリック
部隊を選ぶときに左クリックで選び、複数の部隊を選ぶときはドラッグで選ぶのだが、まとまっている部隊を抽出したいと思った時に便利なコマンドだ。
ドラッグだとこのようにしか選べないが
こういう選び方もできるようになる。
右クリック長押し
選んだ部隊を移動させるには移動してほしい場所に右クリックすればよいのは知っての通り。その時に長押しすると、移動した先での戦列の方向を予約することができる。戦列の方向は部隊の死傷率に直結する項目なので非常に重要だ。
複数部隊選択+右クリック長押し+マウス移動
この時代の戦争は戦列を整えることは非常に重要で、ゲーム的にも複数の部隊が整列していることは何も考えないばらばらの配置と比べるとはるかに強力だ。
しかしいちいち複数の部隊をクリックで整列させることは面倒である。そこで、このコマンドを使えば移動先で各部隊を引かれた線に応じて整列させることができる。
基本的に初歩的な操作と今解説した3つの操作を覚えているだけで最低難易度は軽くクリアできるだろう。逆に言えばかなり重要な操作だ。
部隊選択時各コマンドの仕様
存外忘れられがちな各操作の仕様について左から一つ一つ解説する。
停止
名の通り停止するのだが、停止状態でこのコマンドを行うと自動で戦列の方向転換をしなくなる。前のバージョンでは射撃も行わなくなってしまっていたのだが、どうやらバグだったようで現在は修正されている。敵の騎兵とかで勝手に方向転換して敵歩兵に側面をさらすような場面では重宝する。ただ何かと使い勝手は悪いので使うような状況にいないほうが良いのは確かだ。
倍速
英語だと「run」つまり駆け足。ただの誤訳である。部隊が駆け足で進むようになり、スタミナ(状態)の消費が激しくなる代わりに移動速度が上昇する。ちなみに部隊の移動速度はその部隊のスタミナの残量に依存するのだが、駆け足は最低移動速度が歩くよりも早いため、スタミナが0の部隊は走らせたほうが結局早かったりする。ちなみに旋回速度も速くなるのでめんどくさかったらrunしっぱなしでよい。
追記:最近知ったのだが駆け足の号令が「double-quick!」らしくこの手のゲームで日本語化が倍速だったりトータルウォーとかで「倍の速さで!」となっているのはこれを直訳しているのが原因らしい
突撃
古来より続く基本にして最強のコマンド。一時的に部隊の格闘能力を底上げする。突撃中は相手部隊にとりつくまで異常な速さでスタミナが減っていくのでなるべくぎりぎりで使うようにしよう。一応突撃中は移動速度も駆け足より早くなっている。スタミナが0になると強制的に解除されてしまうので注意。
後退
実は最も重要なコマンド。このガイドを読んでいる人ならわかると思うが、敵からの攻撃を戦列の横や後ろから受けると側面攻撃判定を食らって大ダメージを受ける。なので負けそうな部隊に対してどう後退させるかというのを悩んでいるプレイヤーは割と多いと思う。そのまま下がらせると背中を撃たれて余計に損害を受けるから、自動退却まで耐えさせる判断をすることも少なくないだろう。このコマンドで下がると側面攻撃判定を受けない。整然とした後退は部隊の士気を落とさない。大体真後ろに行ってくれるのも便利だ。
統合
複数の部隊を統合する。利点がよくわからない。精々部隊消滅しそうな部隊をくっつけるぐらいだろうか。
散兵分離
歩兵のみ行えるアクション。歩兵の戦列から小規模な散兵部隊を作り出す。偵察させたり側面に回らせたり、まとめて迂回起動を行わせたりいろいろ使ってみよう。
射撃禁止
あまり使うことのないコマンドだと思うが、砲兵に関してはたまに敵AIの砲兵のカウンターを受けないために禁止にするという方法もある。
退却
即座に自動退却のアレを起こす。自動退却と違うのは好きなタイミングで復帰させることができる点だ。後退と何が違うのっていうとそこまで違いはない。ただ格闘戦時の離脱する速度はこちらのほうが早い。射撃戦は後退、格闘戦は退却。覚えておこう。注意点としてこちらは停止か何か後で指示を与えておかないとマップ外に部隊が消える。
部隊マネジメント
部隊マネジメント
このゲームにおけるマイクロマネジメント要素を解説しようと思う。直感的に面を押し合いへし合いしていくこのゲームにどういうマイクロマネジメント要素があるのかというと士気とカバー値が主になる。
カバー値は説明しなくてもいいだろう。なるべく何もない平原で撃ち合わず、森や都市なければ小麦畑に部隊を隠し攻撃する。常に具体的な数値は表示されるので少しこのゲームになれたなら凝視し続けることになる項目だ。
では士気はどうかというと50と20に注視するべきである。
このゲーム部隊の自動退却以外に3つの状態が存在する。1つは士気が50以上の状態。元気いっぱいで常に最高火力を発揮し続けてくれる。2つ目は50未満になったとき、プレイヤーの操作を受け付けるものの戦列射撃を行えなくなっている。3つ目はさらに減って20未満、この状態になるとプレイヤーの操作は受け付けず、また戦列射撃も行わない。さらにここから減ると自動退却が起きる。基本的には50未満になった部隊は下がらせたほうが良い。Fキーの後退でこれ以上の損害が出る前に後退しよう。
もう一つ50未満になった部隊を下がらせたほうがいい理由がある。士気の回復は3種類あり、それぞれ時間経過、軍団長の補正円内、そして敵への与ダメージである。50未満になった部隊は戦列射撃が行えず敵へのダメージ回復が行えないので加速度的に崩れていく。(一応攻撃を全く行わないわけではない、半減ぐらいのイメージでいいと思う。)
ちなみにスタミナは別に気にしなくてよい。めんどくさかったらずっとはしりっぱで構わない。
マイクロマネジメント…言葉の通り細かいマネジメント。細かい操作をかっこよく言い換えたもの。ラーメンでもなんでも細いほうがスープの味が絡んで美味しくなるかと思いきや小麦の風味が消えたりと良いことばかりではないのだが、親より先に死んだら河原で小石を拾わなければならないので細かい作業は好きであって損はない。
工事中
工事中…